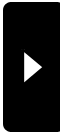2012年05月09日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part8
みなさん
こんばんは
代表の狩俣です


さて、今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「権威でしつけることは”しつけ”ではなく”おしつけ”」です
しつけをする場合、それが親子関係でも、職人社会でも、会社の上下関係でもそうですが、上に立つものはどうしても「権威」を振りかざしがちです
これは知らず知らずの内に誰もが陥ってしまいがちな罠です

権威主義に陥った時、人は人を力ずくで支配しようとします
親は幼い子どもよりも、物理的にも精神的にも”力”があります
どんなに子どもが反抗しても力で押さえつけることができるのです
あるいは、心理的なプレッシャーを与えることもできます
それはとても簡単に出来てしますので、注意しないと容易に行使してしまいます
人間の基本的な行動原理みたいなものです
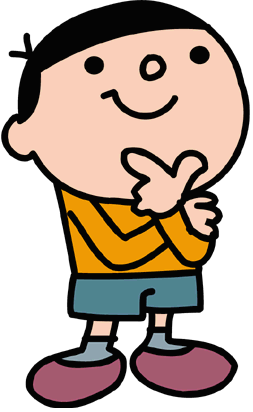
しかし、権威で人を押し付けることには限界があります
人は、確かに厳しく怒られるということを聞きますが、それは「怒られる恐怖」から逃れようとしているだけにすぎません
なぜ、それをしてはいけないのか、という根本的な理解につながることはありません
怒られないように失敗を隠すためなら、嘘をついてでも他人を陥れてもいいと、そういう発想になりかねません
怖い人の言うことは聞くけれど、優しい人のいうことは聞かないということもあるでしょう
親に恨みをつのらせ、親よりも強い力を得た時に激しい反抗や親への暴力となって表面化することもあるかもしれません
しつけには注意が必要です
子どもから自主性を奪ったり、正義感を奪ったりしてしまいます
次回のテーマは「”なぜ、そうしなくてはならないないか”がしつけの原点」です
ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね
kids.powers@gmail.com

にほんブログ村

こんばんは

代表の狩俣です


ところで、みなさんは沖縄では有名な「シーサー」を知っていますよね
名前の由来について調べてみたので載せておきます
沖縄では獅子のことをシーサーとよびます。方言では「しーし」とも呼びます
シルクロードの時代、西域ではライオンのことを「シ(SHE)」と読んでいたそうです
中国では、この「シ」という音に「獅」の字を当て獅子とつけました
ちなみに 「子」については、中国語によく見受けられる敬称で特別な意味はないそうです
この獅子の文字が沖縄に伝来し、シーサーあるいはシーシと沖縄風に発音されていると考えられて
います

名前の由来について調べてみたので載せておきます

沖縄では獅子のことをシーサーとよびます。方言では「しーし」とも呼びます

シルクロードの時代、西域ではライオンのことを「シ(SHE)」と読んでいたそうです

中国では、この「シ」という音に「獅」の字を当て獅子とつけました

ちなみに 「子」については、中国語によく見受けられる敬称で特別な意味はないそうです

この獅子の文字が沖縄に伝来し、シーサーあるいはシーシと沖縄風に発音されていると考えられて
います


さて、今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「権威でしつけることは”しつけ”ではなく”おしつけ”」です

しつけをする場合、それが親子関係でも、職人社会でも、会社の上下関係でもそうですが、上に立つものはどうしても「権威」を振りかざしがちです

これは知らず知らずの内に誰もが陥ってしまいがちな罠です


権威主義に陥った時、人は人を力ずくで支配しようとします

親は幼い子どもよりも、物理的にも精神的にも”力”があります

どんなに子どもが反抗しても力で押さえつけることができるのです

あるいは、心理的なプレッシャーを与えることもできます

それはとても簡単に出来てしますので、注意しないと容易に行使してしまいます

人間の基本的な行動原理みたいなものです

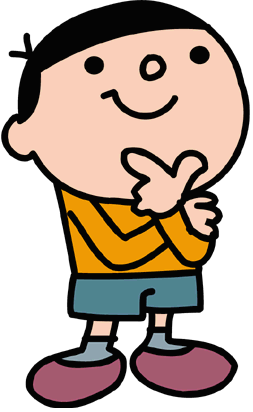
しかし、権威で人を押し付けることには限界があります

人は、確かに厳しく怒られるということを聞きますが、それは「怒られる恐怖」から逃れようとしているだけにすぎません

なぜ、それをしてはいけないのか、という根本的な理解につながることはありません

怒られないように失敗を隠すためなら、嘘をついてでも他人を陥れてもいいと、そういう発想になりかねません

怖い人の言うことは聞くけれど、優しい人のいうことは聞かないということもあるでしょう

親に恨みをつのらせ、親よりも強い力を得た時に激しい反抗や親への暴力となって表面化することもあるかもしれません

しつけには注意が必要です

子どもから自主性を奪ったり、正義感を奪ったりしてしまいます

次回のテーマは「”なぜ、そうしなくてはならないないか”がしつけの原点」です

ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね

kids.powers@gmail.com
にほんブログ村
2012年05月07日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part7
みなさん!
こんばんは
代表の狩俣憂(かりまた すぐる)こと「カーリー」です


さっ
本題に入りましょう
今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「権威主義のしつけには限界がある」です
前回の記事では「権威主義のしつけ」と「児童中心主義のしつけ」があり、それが権威主義から児童中心主義に現代が変わってきているという話をしました
前回はその2つの主義の定義を大きくざっくりとお話しましたが、今回はもう少し中に入っていきましょう
では、なぜ、しつけの仕方が変わってきたのでしょうか

過去のしつけは「型」を教え込むしつけでした

「みずまきはこうまきなさいよ」「お風呂はこう沸かしなさいよ」とそのようなやり方を教えられ、「大人の言われた通りにしなさい」という大人が良しとする「型」に合わせていれば、世の中普通に生きていけたのです
しかし、今の社会は価値観やそれに基づく行動が多様化しています
親が考える価値観を受け継いでも、次の時代にそれが通用するという保証はどこにもありません
自分で考え、判断し、答えを出したり、人と協力して学び合ったり、たとえ何かに失敗しても工夫して直していける生きる力を持つ子を育てていかなければならないのです
「お母さんの言うことや大人の言うことをすべて従おう」では太刀打ちできないのです

私狩俣も小学校の時は携帯電話を持っていないのが普通でしたが、今や子どもたちが携帯を持つ時代になってしまってますからね
時代の変化の早さに驚きを隠せません
社会は急速に変化しています
ほんの20年前には考えられなかったパソコンの普及、携帯電話の普及、ネット社会などなど
地球環境も大きく変化していますし、国際化により国際交流によって様々な国々の価値やルールが混在するようになってきています

そのようななかで、求められる人材は常に変化するのです
大人から教えられた「型」を忠実に学んで覚えこんだところで、それは数年後には古い肩になってしまうかもしれないのです
親の望んだとおりの子になったとしても、新しい社会に適応できるとは限らない
親は、子どもに自分をできれば超えて成長してほしい。新入社員を会社が受け入れる時、新しい風が吹くことを先輩社員は期待するものです
それは、新たな社会に柔軟に適応し、想像力豊かで、新たなものを開拓できるような新しい世代を育てたいと考えている、望んでいるからに違いありません
今回はここまで、また次回に
次回のテーマは「権威でしつけることは”しつけ”ではなく、”おしつけ”」です
ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね
kids.powers@gmail.com

にほんブログ村
こんばんは

代表の狩俣憂(かりまた すぐる)こと「カーリー」です


本題に入る前に・・・
去年2011年度の子どもの流行語を紹介したいと思います
【2011年はやった言葉は?(男の子)】
第1位 ゆるしてニャン(嗣永桃子)
第2位 ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー(あやまんJAPAN)
第3位 マル・マル・モリ・モリ!(薫と友樹、たまにムック。)
【2011年はやった言葉は?(女の子)】
第1位 ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー(あやまんJAPAN)
第2位 マル・マル・モリ・モリ!(薫と友樹、たまにムック。)
第3位 ゆるしてニャン(嗣永桃子)
ホントでしょうか
私が住んでいる沖縄県で「ゆるしてニャン」なんて言っている子は聞いたことがないような気が・・・
しかも、どういう時に使うのでしょうかね


去年2011年度の子どもの流行語を紹介したいと思います

【2011年はやった言葉は?(男の子)】
第1位 ゆるしてニャン(嗣永桃子)
第2位 ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー(あやまんJAPAN)
第3位 マル・マル・モリ・モリ!(薫と友樹、たまにムック。)
【2011年はやった言葉は?(女の子)】
第1位 ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー(あやまんJAPAN)
第2位 マル・マル・モリ・モリ!(薫と友樹、たまにムック。)
第3位 ゆるしてニャン(嗣永桃子)
ホントでしょうか

私が住んでいる沖縄県で「ゆるしてニャン」なんて言っている子は聞いたことがないような気が・・・

しかも、どういう時に使うのでしょうかね



さっ

本題に入りましょう

今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「権威主義のしつけには限界がある」です

前回の記事では「権威主義のしつけ」と「児童中心主義のしつけ」があり、それが権威主義から児童中心主義に現代が変わってきているという話をしました

前回はその2つの主義の定義を大きくざっくりとお話しましたが、今回はもう少し中に入っていきましょう

では、なぜ、しつけの仕方が変わってきたのでしょうか


過去のしつけは「型」を教え込むしつけでした


「みずまきはこうまきなさいよ」「お風呂はこう沸かしなさいよ」とそのようなやり方を教えられ、「大人の言われた通りにしなさい」という大人が良しとする「型」に合わせていれば、世の中普通に生きていけたのです

しかし、今の社会は価値観やそれに基づく行動が多様化しています

親が考える価値観を受け継いでも、次の時代にそれが通用するという保証はどこにもありません

自分で考え、判断し、答えを出したり、人と協力して学び合ったり、たとえ何かに失敗しても工夫して直していける生きる力を持つ子を育てていかなければならないのです

「お母さんの言うことや大人の言うことをすべて従おう」では太刀打ちできないのです


私狩俣も小学校の時は携帯電話を持っていないのが普通でしたが、今や子どもたちが携帯を持つ時代になってしまってますからね

時代の変化の早さに驚きを隠せません

社会は急速に変化しています

ほんの20年前には考えられなかったパソコンの普及、携帯電話の普及、ネット社会などなど

地球環境も大きく変化していますし、国際化により国際交流によって様々な国々の価値やルールが混在するようになってきています


そのようななかで、求められる人材は常に変化するのです

大人から教えられた「型」を忠実に学んで覚えこんだところで、それは数年後には古い肩になってしまうかもしれないのです

親の望んだとおりの子になったとしても、新しい社会に適応できるとは限らない

親は、子どもに自分をできれば超えて成長してほしい。新入社員を会社が受け入れる時、新しい風が吹くことを先輩社員は期待するものです

それは、新たな社会に柔軟に適応し、想像力豊かで、新たなものを開拓できるような新しい世代を育てたいと考えている、望んでいるからに違いありません

今回はここまで、また次回に

次回のテーマは「権威でしつけることは”しつけ”ではなく、”おしつけ”」です

ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね

kids.powers@gmail.com
にほんブログ村
2012年05月06日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part6
みなさん
こんばんは
代表の狩俣です


さぁて、本題に入っていきましょう
今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「権威主義のしつけ、児童中心主義のしつけ」です
前回の記事をご覧になっていない方はご覧になってから、またこのページに戻ってきてください
前回はしつけとはざっくり言いすぎると子どもが社会で生きていくために必要なものということをお教えしました
けれど、多くの親がしつけの方法に悩み事から分かるように、上手にしつけることはとても難しいことです
当然ですが、生まれたばかりの赤ちゃんは、お腹がすいたら泣き、ウンチをすれば泣いて親を呼びます
親は「はいはい、ウンチしまちゅたね~」「お腹がすいたでちゅか~?」なんてことをいってすべての世話をしてくれます

いつの間にか、「快適」な状態に戻してくれる、それが当たり前でした
しかし、寝返りやハイハイが始まり、赤ちゃんが自分の意志で行動するようになり、しつけがスタートしたとたん赤ちゃんの世界は劇的にビフォーアフターで世界が一変します
ほとんど満たされていたはずの欲求に「ダメ」がついてきます
バトルの始まりです
「嫌だ!」「やりたくない!!」という赤ちゃんの欲求と「ダメよ」「やりなさい」というお母さんの思い

過去の日本は、そのようなバトルは親の勝利に終わることが多かったようです
以前の日本は大人の言うことは絶対で、口ごたえは許されなかったからです
それでも言うことを聞かない子は、叩かれたり、されました
愛のムチですね
大人はその権力と腕力で子どもを押さえつけることでしつけに成功していたのです
いわゆる、「権威主義」でした
だが、しかし、時代は大きく変わりましたよね
欧米から伝わってきた「児童中心主義」の考え方が広まり、子どもを一人の人間として尊重し、その個性や発達段階を重視してしつけや教育を行うようになっていきました
型を押し付けたいり、矯正したりするよりも、子どもの個性を尊重し、自分で考え、判断し、意思決定する力を育てていこう、主体性を育てていこう言う教育方針に転換されました
私狩俣ももちろん「児童中心主義」の時代で育ちましたよ

「じゃあさ~。大人よりも子どもの都合を優先させるってこと?」なんてこえが聞こえてきそうなんですが、子どもの言いなりになるということではないです
大人が幼い子供の発達や個性を理解して、子供自身が納得できるように、価値やルールを示すということです
そして、それを子ども自身が自分の力で自分の内側に取り込めるように、働きかけていくということです
あくまで、子ども中心にして考えるという姿勢こそが、もっとも効果的にしつけを定着させられるとそう考えられているのです
今回は少し、硬すぎたお話になってしまいましたが、この「権威主義」と「児童中心主義」の考え方も知識として頭にいれていて欲しいです
今後の記事で大きく関係してくるので覚えていてくださいね
次回のテーマはなぜ、時代は変わってきたのか。「権威主義のしつけには、限界がある」です
楽しみにしててくださいね
ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね
kids.powers@gmail.com

こんばんは

代表の狩俣です


まだ5月というのに沖縄県はもう夏ですね
ちなみに私狩俣のGWはずっと読書や大学の課題をしていました
でも、ドライブで海まで行ってきましたよ
みなさんのGWの思い出も聞いてみたいものですね
BBQは定番でしょうか?
遊園地や水族館でしょうか?
沖縄で言うと那覇ハーリーがありましたね
GWも今日で終わりですので、また明日から普段の平日が戻ってきます
明日仕事の方はGW明けは思い出話で盛り上がりそうですね
なんかお土産も期待してしまいますね
明日からも頑張っていきましょう

ちなみに私狩俣のGWはずっと読書や大学の課題をしていました

でも、ドライブで海まで行ってきましたよ

みなさんのGWの思い出も聞いてみたいものですね

BBQは定番でしょうか?

遊園地や水族館でしょうか?

沖縄で言うと那覇ハーリーがありましたね

GWも今日で終わりですので、また明日から普段の平日が戻ってきます

明日仕事の方はGW明けは思い出話で盛り上がりそうですね

なんかお土産も期待してしまいますね

明日からも頑張っていきましょう


さぁて、本題に入っていきましょう

今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「権威主義のしつけ、児童中心主義のしつけ」です

前回の記事をご覧になっていない方はご覧になってから、またこのページに戻ってきてください

前回はしつけとはざっくり言いすぎると子どもが社会で生きていくために必要なものということをお教えしました

けれど、多くの親がしつけの方法に悩み事から分かるように、上手にしつけることはとても難しいことです

当然ですが、生まれたばかりの赤ちゃんは、お腹がすいたら泣き、ウンチをすれば泣いて親を呼びます

親は「はいはい、ウンチしまちゅたね~」「お腹がすいたでちゅか~?」なんてことをいってすべての世話をしてくれます


いつの間にか、「快適」な状態に戻してくれる、それが当たり前でした

しかし、寝返りやハイハイが始まり、赤ちゃんが自分の意志で行動するようになり、しつけがスタートしたとたん赤ちゃんの世界は劇的にビフォーアフターで世界が一変します

ほとんど満たされていたはずの欲求に「ダメ」がついてきます

バトルの始まりです

「嫌だ!」「やりたくない!!」という赤ちゃんの欲求と「ダメよ」「やりなさい」というお母さんの思い


過去の日本は、そのようなバトルは親の勝利に終わることが多かったようです

以前の日本は大人の言うことは絶対で、口ごたえは許されなかったからです

それでも言うことを聞かない子は、叩かれたり、されました

愛のムチですね

大人はその権力と腕力で子どもを押さえつけることでしつけに成功していたのです

いわゆる、「権威主義」でした

だが、しかし、時代は大きく変わりましたよね

欧米から伝わってきた「児童中心主義」の考え方が広まり、子どもを一人の人間として尊重し、その個性や発達段階を重視してしつけや教育を行うようになっていきました

型を押し付けたいり、矯正したりするよりも、子どもの個性を尊重し、自分で考え、判断し、意思決定する力を育てていこう、主体性を育てていこう言う教育方針に転換されました

私狩俣ももちろん「児童中心主義」の時代で育ちましたよ


「じゃあさ~。大人よりも子どもの都合を優先させるってこと?」なんてこえが聞こえてきそうなんですが、子どもの言いなりになるということではないです

大人が幼い子供の発達や個性を理解して、子供自身が納得できるように、価値やルールを示すということです

そして、それを子ども自身が自分の力で自分の内側に取り込めるように、働きかけていくということです

あくまで、子ども中心にして考えるという姿勢こそが、もっとも効果的にしつけを定着させられるとそう考えられているのです

今回は少し、硬すぎたお話になってしまいましたが、この「権威主義」と「児童中心主義」の考え方も知識として頭にいれていて欲しいです

今後の記事で大きく関係してくるので覚えていてくださいね

次回のテーマはなぜ、時代は変わってきたのか。「権威主義のしつけには、限界がある」です

楽しみにしててくださいね

ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね

kids.powers@gmail.com
2012年05月06日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part5
みなさん!
こんばんは
代表の狩俣です


さぁて、今回の子育て豆知識の内容に入っていこうと思います
今回のテーマは「そもそも”しつけ”ってなんだろう?」です
ここで、少しだけしつけの目的について考えてみたいと思います
しつけとは、人間が社会の中で生きていくために必要な価値やルール、他者との関わり方、必要に応じた自己コントロールの仕方等を子どもに伝え、こどお自信が納得して学べるように仕掛けていくことです
子どもが人や社会にうまく折り合いをつけながら、発達していくことを「社会化」と呼んでいますが、子どもがうまく社会化されていくためには、その社会にあらかじめ存在する「価値」や「ルール」を学ぶ必要があります
そのために必要なのが”しつけ”です
もしも、我が子が無人島で一人で暮らしていくのなら必要ないです。しかし、社会あ人との関わりで成り立っています
他者と折り合いをつけていくことが、生きるために必要条件となります
目に見える決まり、見えない決まり、文章化された決まり、暗黙の了解等それこそが数えきれないほどたくさんの価値やルールが存在し、それを学んでいかないと、生きていくことさえ不自由になってしまいます

しかし、幼い子はそれを知りません
なぜなら、まだ数年しか生きていないのですから、何が大切か、どういう基準があるのか、それを守ることが必要なのか、どのように行動すればいいのかが全くわからないのです
確かに、私狩俣も小さい子どもに「これはダメだよ」ということがありますが、なかなか聞いてくれないことがほとんどです
それで、イライラしてしまうこともあります
しかし、社会の価値やルールがわからないだけと考えるだけでなんかその子の気持ちや行動がわかないわけでもない気がしてきました
しっかりと教えてあげなくては

子どもがそれらを学ぶために、私たち大人は子どもにしつけとして、社会の価値やルールを伝達していかなければなりません
社会の維持、発展させていくために、なくてはならないのです
もちろん、親だけがしつけをするわけではありません
社会も参加しなくてはいけません
幼稚園、保育園、学校などで同年齢や異年齢の仲間や先生とかかわり合っていくことでも、価値やルールが身についていきます
親は、その両方を大切にしていきながら、子どもが社会に適応できるように育てていかなくてはいけないのですよ
次回のテーマは「権威主義のしつけ、児童中心のしつけ」です
お楽しみに~
こんばんは

代表の狩俣です


GWの真っ最中ですが、みなさんはどのようにこの連休をお過ごしですか
「子どもの日」ということもありまして家族みんなで、お出かけして遊園地や水族館に遊びに行ったりしているでしょうか

私の沖縄県では、ちゅら海水族館が子どもたちが特に喜んでくれますね
キャッキャ騒いで楽しそうです
みなさんは、そもそも子どもの日には欠かせない”鯉のぼり”の由来って知ってますか
調べたことなんですが・・・
鯉のぼりには、人生という流れの中で遭遇する難関を鯉のように突破して立身出世して欲しい、という願いが込められており、古代中国の故事に由来します
中国の黄河上流に竜門という激流が連なる滝があり、そこを登り切った魚は霊力が宿って龍になるといわれていました
その滝を登るほどの勢いのある淡水魚は、清流のみならず池や沼地などでも生息できる生命力の強い鯉をおいてほかにありません
ある時、一匹の鯉が激しい滝水に逆らいながら竜門を登りきったところ、鯉は龍へと変身し天に昇っていきました
中国では龍は皇帝の象徴でもあり、とても縁起のいいものなのです
この「登竜門」 という故事が、立身出世の関門を示すお馴染みの慣用句の語源ですし、「滝」という漢字もこの故事に由来しています。また、古代中国の超エリートである官吏登用試験制度の科挙の試験場の正門も「竜門」と呼ばれています
わからなかった方はまた一つ豆知識が増えましたね

「子どもの日」ということもありまして家族みんなで、お出かけして遊園地や水族館に遊びに行ったりしているでしょうか


私の沖縄県では、ちゅら海水族館が子どもたちが特に喜んでくれますね

キャッキャ騒いで楽しそうです

みなさんは、そもそも子どもの日には欠かせない”鯉のぼり”の由来って知ってますか

調べたことなんですが・・・

鯉のぼりには、人生という流れの中で遭遇する難関を鯉のように突破して立身出世して欲しい、という願いが込められており、古代中国の故事に由来します

中国の黄河上流に竜門という激流が連なる滝があり、そこを登り切った魚は霊力が宿って龍になるといわれていました

その滝を登るほどの勢いのある淡水魚は、清流のみならず池や沼地などでも生息できる生命力の強い鯉をおいてほかにありません

ある時、一匹の鯉が激しい滝水に逆らいながら竜門を登りきったところ、鯉は龍へと変身し天に昇っていきました

中国では龍は皇帝の象徴でもあり、とても縁起のいいものなのです

この「登竜門」 という故事が、立身出世の関門を示すお馴染みの慣用句の語源ですし、「滝」という漢字もこの故事に由来しています。また、古代中国の超エリートである官吏登用試験制度の科挙の試験場の正門も「竜門」と呼ばれています

わからなかった方はまた一つ豆知識が増えましたね


さぁて、今回の子育て豆知識の内容に入っていこうと思います

今回のテーマは「そもそも”しつけ”ってなんだろう?」です

ここで、少しだけしつけの目的について考えてみたいと思います

しつけとは、人間が社会の中で生きていくために必要な価値やルール、他者との関わり方、必要に応じた自己コントロールの仕方等を子どもに伝え、こどお自信が納得して学べるように仕掛けていくことです

子どもが人や社会にうまく折り合いをつけながら、発達していくことを「社会化」と呼んでいますが、子どもがうまく社会化されていくためには、その社会にあらかじめ存在する「価値」や「ルール」を学ぶ必要があります

そのために必要なのが”しつけ”です

もしも、我が子が無人島で一人で暮らしていくのなら必要ないです。しかし、社会あ人との関わりで成り立っています

他者と折り合いをつけていくことが、生きるために必要条件となります

目に見える決まり、見えない決まり、文章化された決まり、暗黙の了解等それこそが数えきれないほどたくさんの価値やルールが存在し、それを学んでいかないと、生きていくことさえ不自由になってしまいます


しかし、幼い子はそれを知りません

なぜなら、まだ数年しか生きていないのですから、何が大切か、どういう基準があるのか、それを守ることが必要なのか、どのように行動すればいいのかが全くわからないのです

確かに、私狩俣も小さい子どもに「これはダメだよ」ということがありますが、なかなか聞いてくれないことがほとんどです

それで、イライラしてしまうこともあります

しかし、社会の価値やルールがわからないだけと考えるだけでなんかその子の気持ちや行動がわかないわけでもない気がしてきました

しっかりと教えてあげなくては


子どもがそれらを学ぶために、私たち大人は子どもにしつけとして、社会の価値やルールを伝達していかなければなりません

社会の維持、発展させていくために、なくてはならないのです

もちろん、親だけがしつけをするわけではありません

社会も参加しなくてはいけません

幼稚園、保育園、学校などで同年齢や異年齢の仲間や先生とかかわり合っていくことでも、価値やルールが身についていきます

親は、その両方を大切にしていきながら、子どもが社会に適応できるように育てていかなくてはいけないのですよ

次回のテーマは「権威主義のしつけ、児童中心のしつけ」です

お楽しみに~

2012年05月04日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part4
こんにちは
代表の狩俣です



さて、「今日の子育て豆知識」のテーマは「しつけは、子どもを生きやすくする」です
前回の記事をごらんになっていない方はご覧になってこのページに戻ってきていただけたらわかりやすいと思います
まだpart4なのですぐに内容を理解できると思います
しつけそのものは、とても大切な親の仕事です
上手にしつけられた子どもは、社会の中でとても生きやすくなります
人を尊重できる人は相手からも尊重されます
ルールを守れる人は信頼されます。家庭内で自分の役割を果たせることは、家族みんなが快適に暮らすことができるのです
子どもにとって、親から与えられた素晴らしいプレゼントになりうるのです

確かに、私狩俣も小さい頃、同じ幼稚園に通っている子に悪いことを言ってしまったことがありました。その時、親にかなり怒られた経験があります
でも、今思うとあれが人の気持ちが分かるようになるいいきっかけになったんだと思います
みなさんもちょっと思い出して見てください!
あなたが10代後半~20代になったばかりの頃、つまり大学生ぐらいの頃です
一人暮らしの友人が部屋を使いやすいように整えていたり、自分の生活をコントロールしているのを見たとき、「この人すごいなぁ~」と思いませんでしたか?
大学生では、一人暮らししているだけですごいと思う人がいるかもしれません
逆に、いつも時間に遅れてしまう人、すぐにモノをなくす人は仕事をするうえでも、勉強をする上でも要領が悪く苦労したことはありませんか?

自分の行動や感情をコントロールして、自律出来る人は魅力的に見えるのです
しつけのメリットは、周りに認められるということだけではありません
感情や行動をコントロール方法を知っていたり、自分の生活を快適にできたりする人は、とても生きやすいのです。
私も、部屋の片付けは苦手で、気を抜いているとすぐにごちゃごちゃになっていることがあるので、一ヶ月に一度はきれいに掃除をしています
掃除すると気持ちもスッキリしますから、イライラしていたり、気持ちが落ち着かないときは掃除するようにしています
上手なしつけは、子どもが将来社会で自立した時に役立つ、大切なプレゼントなのだと思います
次回は「そもそもしつけってなんだろう?」についてお話していこうと思います
お楽しみに~
ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね
kids.powers@gmail.com
参考文献:「こどものしつけがわかる本」 著者:岩立 京子

代表の狩俣です


今日は感動する詩を紹介したいと思います!

みつをさんの詩です
なんか心にぐっとくるものがあったので載せてみました
みつをさんの大ファンになってしまいます
この詩を見て何か感じてくれたら載せた私も嬉しいです!

なんか心にぐっとくるものがあったので載せてみました

みつをさんの大ファンになってしまいます

この詩を見て何か感じてくれたら載せた私も嬉しいです!

さて、「今日の子育て豆知識」のテーマは「しつけは、子どもを生きやすくする」です

前回の記事をごらんになっていない方はご覧になってこのページに戻ってきていただけたらわかりやすいと思います

まだpart4なのですぐに内容を理解できると思います

しつけそのものは、とても大切な親の仕事です

上手にしつけられた子どもは、社会の中でとても生きやすくなります

人を尊重できる人は相手からも尊重されます

ルールを守れる人は信頼されます。家庭内で自分の役割を果たせることは、家族みんなが快適に暮らすことができるのです

子どもにとって、親から与えられた素晴らしいプレゼントになりうるのです


確かに、私狩俣も小さい頃、同じ幼稚園に通っている子に悪いことを言ってしまったことがありました。その時、親にかなり怒られた経験があります

でも、今思うとあれが人の気持ちが分かるようになるいいきっかけになったんだと思います

みなさんもちょっと思い出して見てください!
あなたが10代後半~20代になったばかりの頃、つまり大学生ぐらいの頃です

一人暮らしの友人が部屋を使いやすいように整えていたり、自分の生活をコントロールしているのを見たとき、「この人すごいなぁ~」と思いませんでしたか?

大学生では、一人暮らししているだけですごいと思う人がいるかもしれません

逆に、いつも時間に遅れてしまう人、すぐにモノをなくす人は仕事をするうえでも、勉強をする上でも要領が悪く苦労したことはありませんか?


自分の行動や感情をコントロールして、自律出来る人は魅力的に見えるのです

しつけのメリットは、周りに認められるということだけではありません

感情や行動をコントロール方法を知っていたり、自分の生活を快適にできたりする人は、とても生きやすいのです。
私も、部屋の片付けは苦手で、気を抜いているとすぐにごちゃごちゃになっていることがあるので、一ヶ月に一度はきれいに掃除をしています

掃除すると気持ちもスッキリしますから、イライラしていたり、気持ちが落ち着かないときは掃除するようにしています

上手なしつけは、子どもが将来社会で自立した時に役立つ、大切なプレゼントなのだと思います

次回は「そもそもしつけってなんだろう?」についてお話していこうと思います

お楽しみに~

ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね

kids.powers@gmail.com
参考文献:「こどものしつけがわかる本」 著者:岩立 京子
2012年05月03日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part3
みなさん!
こんばんは
代表の狩俣です

今日は気持ちいい青空が広がっていましたね
お出かけ日和でGWには最高の天気です
新都心公園を僕がちょっと歩いて通っていたのですが、子どもたちがキャッキャと楽しそうな声をあげて遊んでいる姿もみれました。
大切なことに気づく場所は、いつも、パソコンの前ではなく、青空の下だった。by高橋歩
まさにその気持ちになりましたね

今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「”しつけ”って本当に必要?」です
内容に入っていこうと思います
まず、「しつけ」という言葉を聞いて、みなさんはどんなイメージを持ちますか

こどもの個性にかかわらず型にはめ込む。親の価値を押し付ける。親の自己満足。そのような考えをしている親はあまりいないと思いますが、そんな悪いイメージを持っていますか?
逆に、子どもが自立するために親が伝える大切なものというプラスのイメージを持っていますか

特に幼いお子さんをお持ちのママさんは、しつけに困っている、迷っている人が少なくないと思います!
厳しいしつけをしてしまうと自主性が育たなくなってしまうのではないか? 最近の親はしつけをしなさすぎる。マナーを守れない子はダメなので私はしっかり育てますわ。 という人もいらっしゃることでしょう
この記事を見ている学生さんも弟、妹の扱いに困っている方もいると思います
僕も塾で子どもたちと関わることが多いので、しつけというより扱い困るその一人です
子どもが小中学生になると、「幼い頃にちゃんとしつけなかったから、こんなことも出来ない子になってしまったわ。わたくししつけが悪かったのかしら。嫌だわ~」という方もいれば、「厳しくしすぎたせいで、子どもが親に反抗的になってしまったわ~」という人もいると思います

しつけの考え方は子どもという存在をどう見るか、あるいはこどもと大人との関係をどう見るかによって変わってきますし、それに伴って実際のしつけ方も変わります。どんなしつけがいいのか、どれが正しいしつけなのかという問いに一つ一つの答えを出せる人等居ないのではないでしょうか
最善の方法のアドバイスぐらいしかできないです
前回でもお話した通り、現代は複雑な社会なので、社会環境が子どもたちに与える影響は大きいのです
なので、今の社会に求められる、新しいしつけを一人一人が考えることが必要ではないかということです
次回は「しつけは、子どもを生きやすくする」です
ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね
kids.powers@gmail.com
こんばんは

代表の狩俣です


今日は気持ちいい青空が広がっていましたね

お出かけ日和でGWには最高の天気です

新都心公園を僕がちょっと歩いて通っていたのですが、子どもたちがキャッキャと楽しそうな声をあげて遊んでいる姿もみれました。
大切なことに気づく場所は、いつも、パソコンの前ではなく、青空の下だった。by高橋歩
まさにその気持ちになりましたね


今回の「今日の子育て豆知識」のテーマは「”しつけ”って本当に必要?」です

内容に入っていこうと思います

まず、「しつけ」という言葉を聞いて、みなさんはどんなイメージを持ちますか


こどもの個性にかかわらず型にはめ込む。親の価値を押し付ける。親の自己満足。そのような考えをしている親はあまりいないと思いますが、そんな悪いイメージを持っていますか?

逆に、子どもが自立するために親が伝える大切なものというプラスのイメージを持っていますか


特に幼いお子さんをお持ちのママさんは、しつけに困っている、迷っている人が少なくないと思います!
厳しいしつけをしてしまうと自主性が育たなくなってしまうのではないか? 最近の親はしつけをしなさすぎる。マナーを守れない子はダメなので私はしっかり育てますわ。 という人もいらっしゃることでしょう

この記事を見ている学生さんも弟、妹の扱いに困っている方もいると思います

僕も塾で子どもたちと関わることが多いので、しつけというより扱い困るその一人です

子どもが小中学生になると、「幼い頃にちゃんとしつけなかったから、こんなことも出来ない子になってしまったわ。わたくししつけが悪かったのかしら。嫌だわ~」という方もいれば、「厳しくしすぎたせいで、子どもが親に反抗的になってしまったわ~」という人もいると思います


しつけの考え方は子どもという存在をどう見るか、あるいはこどもと大人との関係をどう見るかによって変わってきますし、それに伴って実際のしつけ方も変わります。どんなしつけがいいのか、どれが正しいしつけなのかという問いに一つ一つの答えを出せる人等居ないのではないでしょうか

最善の方法のアドバイスぐらいしかできないです

前回でもお話した通り、現代は複雑な社会なので、社会環境が子どもたちに与える影響は大きいのです

なので、今の社会に求められる、新しいしつけを一人一人が考えることが必要ではないかということです

次回は「しつけは、子どもを生きやすくする」です

ブログの内容に関する質問やPOWERSに興味がある方は☟のアドレスに気軽に送信してね

kids.powers@gmail.com
2012年05月02日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part2
こんにちは!
代表の狩俣です

先日、僕がそろばんを教えている塾の生徒が珠算検定試験で段位を取りました
「バンザーイ 」「おめでとう
」「おめでとう 」
」
子どもたちの頑張る姿に僕も元気をもらえています
子どもたちが一生懸命前に進んでいる、僕も負けてられません
でも、遊んでいるといつもうるさい子どもたちが試験になると見違えるようにそろばんを弾くスゴワザを見ると子どもは見た目ではわからない才能と集中力が隠されているなと感じます
嬉しいです

さて、この話はさて置き、本題に入って行きましょう
今回のテーマは「子育ての責任が親だけにあるとは限らない」です
前回は現代の子育ては子どもの犯罪も多くなっていることや情報が多く飛び交うようになったため難しくなってきたという話をしました

そのような非行に走ってしまった子どもは責任は母親だけにあるというわけではありません
やはり、子どもが問題を起こせば、必ず責められるのが親です。母親の愛情が不足していた、母親の厳格さが子どもを追い詰めた、こんなことしている子の親の顔が見てみたいわ、とかまるですべて親が悪いと言わんばかりです
普通に育てれば、育つと多くの人は思っているのかもしれません
だから、問題が起きた時は「間違った育て方をしたのだ」とおもうのでしょう

しかし、問題はこんなに簡単ではありません
普通に育てればという”普通”とはどういうことでしょう
人が社会の中で育つということはそれほど簡単なことではありません
問題が起きる可能性は誰もが持っているのです
この問題の背景には、家族関係、友人関係、学校の問題、病気など様々です
いい子に育つことが当然で、それができない母親は失格なのだとそんなふうに考えてしまったら誰も子どもなんて育てられません
子どもは社会の中で育っていくのです
親は確かに特別な存在かもしれません。
それ以外にも学校の教師、友達、また子どもを取り巻く社会の環境全てがこどもに大きな影響を及ぼしているのです
子育ては母親だけがすることではありません
私たちが生きている社会が子どもたちを育てているという意識を持つことが大事だと思います

POWERSもそのような子育ての一員でありたいですね
力になりたいですね
けっして母親一人が原因で子どもがどうこうなってしまうわけではないということです
次回は本格的にしつけの話に入っていこうと思います
テーマは「”しつけ”って本当に必要なの?」です
POWERSに興味がある方は是非メールください!
kids.powers@gmai.com
代表の狩俣です


先日、僕がそろばんを教えている塾の生徒が珠算検定試験で段位を取りました

「バンザーイ
 」「おめでとう
」「おめでとう 」
」子どもたちの頑張る姿に僕も元気をもらえています

子どもたちが一生懸命前に進んでいる、僕も負けてられません

でも、遊んでいるといつもうるさい子どもたちが試験になると見違えるようにそろばんを弾くスゴワザを見ると子どもは見た目ではわからない才能と集中力が隠されているなと感じます

嬉しいです


さて、この話はさて置き、本題に入って行きましょう

今回のテーマは「子育ての責任が親だけにあるとは限らない」です

前回は現代の子育ては子どもの犯罪も多くなっていることや情報が多く飛び交うようになったため難しくなってきたという話をしました


そのような非行に走ってしまった子どもは責任は母親だけにあるというわけではありません

やはり、子どもが問題を起こせば、必ず責められるのが親です。母親の愛情が不足していた、母親の厳格さが子どもを追い詰めた、こんなことしている子の親の顔が見てみたいわ、とかまるですべて親が悪いと言わんばかりです

普通に育てれば、育つと多くの人は思っているのかもしれません

だから、問題が起きた時は「間違った育て方をしたのだ」とおもうのでしょう


しかし、問題はこんなに簡単ではありません

普通に育てればという”普通”とはどういうことでしょう

人が社会の中で育つということはそれほど簡単なことではありません

問題が起きる可能性は誰もが持っているのです

この問題の背景には、家族関係、友人関係、学校の問題、病気など様々です

いい子に育つことが当然で、それができない母親は失格なのだとそんなふうに考えてしまったら誰も子どもなんて育てられません

子どもは社会の中で育っていくのです

親は確かに特別な存在かもしれません。
それ以外にも学校の教師、友達、また子どもを取り巻く社会の環境全てがこどもに大きな影響を及ぼしているのです

子育ては母親だけがすることではありません

私たちが生きている社会が子どもたちを育てているという意識を持つことが大事だと思います


POWERSもそのような子育ての一員でありたいですね

力になりたいですね

けっして母親一人が原因で子どもがどうこうなってしまうわけではないということです

次回は本格的にしつけの話に入っていこうと思います

テーマは「”しつけ”って本当に必要なの?」です

POWERSに興味がある方は是非メールください!
kids.powers@gmai.com
2012年05月01日
今日の子育て豆知識 ~子どものしつけ編~ part1
みなさん!こんにちは!
代表の狩俣です
最近はじめじめとしたお天気と変わり易い空模様でイライラしますよね
沖縄県が梅雨歴三番目に早い梅雨入りをしたそうです
夏はもう間近というところでしょうか?

まぁ、それはさて置き、今日も豆知識の時間がやってきました
今回は新しい豆知識の分野に入っていきます!
前回は「子どものやる気」にフォーカスしてお話をしてきました
今回からは「子どものしつけ方法」についてお話していこうと思います

今回記念すべき第一回目のテーマは「子育てが難しいと言われているわけ」についてです
第一回ということもありますので、まずすぐに内容にはいるということはしません
第三回ぐらいまではしつけの前に子育てということについて話していこうと思います

子育ての世界では、様々な情報が飛び交い、「○○歳までに○○できないと発達が遅すぎる」という真偽の定かではない情報が様々な方向から入ってきます。
今は、昔とちがって一人~二人の子どもを育てる傾向があるので、「少ない子どもをちゃんとそだてなくちゃ」というプレッシャーも大きくなりがちです
また、「ママになっても綺麗でいなくちゃ」「ママになっても金メダル」というメッセージが強く、育児だけでも大変なのに、ファッションや「育児も両方やっている人が輝いている!」なんてメッセージもあって悩んでしまう人も少なくありません

それでも、我が子がしっかりと育ってくれれば、毎日、子育てと奮闘するかいもありますが、必ずしも子どもが期待通りに成長してくれるとは限りません
今の現代は、少年犯罪のニュースが増えています

子どもがいじめの加害者や被害者になってしまった事件、中学生が刃物でクラスメートを刺してしまった事件、幼い子を殺害してしまうという事件も新聞やTVで報道されました
そういう真偽が定かでは無い情報や子どもが事件を起こすかもしれないという不安から子育てが難しいと言われているわけだと思います
次回は、「子育ての責任は親だけにあるんじゃない」についてお話していきます
フェイスブックページもあります https://www.facebook.com/kids.POWERS
代表の狩俣です

最近はじめじめとしたお天気と変わり易い空模様でイライラしますよね

沖縄県が梅雨歴三番目に早い梅雨入りをしたそうです

夏はもう間近というところでしょうか?


まぁ、それはさて置き、今日も豆知識の時間がやってきました

今回は新しい豆知識の分野に入っていきます!
前回は「子どものやる気」にフォーカスしてお話をしてきました

今回からは「子どものしつけ方法」についてお話していこうと思います


今回記念すべき第一回目のテーマは「子育てが難しいと言われているわけ」についてです

第一回ということもありますので、まずすぐに内容にはいるということはしません

第三回ぐらいまではしつけの前に子育てということについて話していこうと思います


子育ての世界では、様々な情報が飛び交い、「○○歳までに○○できないと発達が遅すぎる」という真偽の定かではない情報が様々な方向から入ってきます。
今は、昔とちがって一人~二人の子どもを育てる傾向があるので、「少ない子どもをちゃんとそだてなくちゃ」というプレッシャーも大きくなりがちです

また、「ママになっても綺麗でいなくちゃ」「ママになっても金メダル」というメッセージが強く、育児だけでも大変なのに、ファッションや「育児も両方やっている人が輝いている!」なんてメッセージもあって悩んでしまう人も少なくありません


それでも、我が子がしっかりと育ってくれれば、毎日、子育てと奮闘するかいもありますが、必ずしも子どもが期待通りに成長してくれるとは限りません

今の現代は、少年犯罪のニュースが増えています


子どもがいじめの加害者や被害者になってしまった事件、中学生が刃物でクラスメートを刺してしまった事件、幼い子を殺害してしまうという事件も新聞やTVで報道されました

そういう真偽が定かでは無い情報や子どもが事件を起こすかもしれないという不安から子育てが難しいと言われているわけだと思います

次回は、「子育ての責任は親だけにあるんじゃない」についてお話していきます

フェイスブックページもあります https://www.facebook.com/kids.POWERS
2012年04月09日
POWERSミーティング 説明会編
皆さんこんばんは
代表の狩俣すぐるです
先日、4月4日にPOWERSミーティングがありました
今回は「サークル説明会」についてサークル説明会の概要とチラシ作成をしました
メンバーの比嘉真理乃さんと比嘉早弥香さんがチラシ作成に熱を入れていました
とても、気合の入っていたのか3時間のミーティングで作成に1時間程でとても綺麗なチラシが出来上がりましたよ

しっかり、サークルの説明会の内容をどうするかずっと考えていました
さて、ここで私たちPOWERSのサークルから告知です
サークル説明会が4月16日に開催します

POWERSのサークル説明会の日程がきまりました
日時:4月16日㈪ 午後5時~6時まで
場所:琉球大学付属図書館 1階 グループ学習室C

説明会後は参加者みんなでお食事会という形で懇親会もありますよ
そこで、参加者と仲良くなるチャンスです

今後5月始めにこどもイベントも企画してますので、随時みなさんにお知らせしていきます
子どもたちの笑顔のために私たちPOWERSは動いています
興味を持ってくれた方は僕に連絡お願いしますね♪
私たちPOWERSはフェイスブックページもあります
https://www.facebook.com/kids.POWERS
今日は、ここまで

代表の狩俣すぐるです

先日、4月4日にPOWERSミーティングがありました

今回は「サークル説明会」についてサークル説明会の概要とチラシ作成をしました

メンバーの比嘉真理乃さんと比嘉早弥香さんがチラシ作成に熱を入れていました

とても、気合の入っていたのか3時間のミーティングで作成に1時間程でとても綺麗なチラシが出来上がりましたよ


しっかり、サークルの説明会の内容をどうするかずっと考えていました

さて、ここで私たちPOWERSのサークルから告知です

サークル説明会が4月16日に開催します


POWERSのサークル説明会の日程がきまりました

日時:4月16日㈪ 午後5時~6時まで
場所:琉球大学付属図書館 1階 グループ学習室C

説明会後は参加者みんなでお食事会という形で懇親会もありますよ

そこで、参加者と仲良くなるチャンスです


今後5月始めにこどもイベントも企画してますので、随時みなさんにお知らせしていきます

子どもたちの笑顔のために私たちPOWERSは動いています

興味を持ってくれた方は僕に連絡お願いしますね♪
私たちPOWERSはフェイスブックページもあります

https://www.facebook.com/kids.POWERS
今日は、ここまで

2012年03月26日
こどものやる気アップ part27
みなさん!
こんにちは
先日、学生観光振興プロジェクトの報告会に参加してきました
一人一人が向上心を持って活動をしている姿や、熱い想い等がひしひしと伝わってきました
僕たちはまだ無限のつぼみです
信じ続けて進みましょう
どんな花も咲かすでしょう
私も、負けないように頑張ります

さて、本日の本題に入っていきますが、その前に前回の記事をご覧になっていない方はご覧になってからこの記事を読んでください
テーマは「うちの子って褒めるところがないってほんと?」についてです
まず、皆さんは子どもをどういう目で見ていますか

子どもは子どもだと思って接しすぎていませんか?
子どもも一人の人間です

「勉強しない、家の手伝いをしない、忘れ物が多いとか、うちの子って褒めるところないんですよ~」なんてそんな言葉をよく聞きます
褒めるところが見つからないというのは、大人が勝手に「ここまでできないとほめられない」と、心のストライクゾーンを狭べているだけではないでしょうか
みなさんは、子どもを思う気持ちが強すぎて、しっかりしなきゃなんて思い過ぎなのかもしれません
もっと無駄に力を入れないでください
「一緒に遊ぶ友達がこんなにいるのは、優しいからだよね」「毎日よく寝て食べているんだから、健康ってことよね。大したもんよ」など、そんな風に広く視点を変えてみてもいいかもしれません
つまり、子どもは自分なりに頑張っているのです
その、頑張りを親の基準に満たないからと押し付けるようなことはしないで欲しいということです
子どもの教育はその子のダメなところ、いいところを見抜いて、見抜いて、我慢をする、見守る能力も必要です
悪いところは子どもが自分自身で気づかせるようにすることも大事です

しかし、褒められないという人の中には褒めることに対して否定的な人がいます
褒め言葉を言うなんて自分らしくない、褒められると落ち着かないと。多くの場合は、自分が褒められずに育ってきた人です
「褒められなかったからこそ頑張れた」とむしろ褒めない育児を肯定しています
しかし、虐待が連鎖するように、褒められない成育歴も連鎖します
たとえ親が今幸せになれたとしても、こどもが同じように幸せに生きられるとは限りませんよ どこかで断ち切ってください
どこかで断ち切ってください
そこまで、重い理由がなくても、親自身の精神状態や身体状態が良くない場合、余裕がなくなってしまって、我が子のいいところが見えなくなってしまいます
子どもの悪いところしか見えないと思ったら、それは親自身のSOSサインです
家族や実家にSOSを出して助けをもらったり、学校カウンセラーに相談してみてらいいかもしれません
そして、頑張っている自分をちゃんと褒めてあげてください

次回は、新しい豆知識に入っていきます
子どものしつけについて中心にしてお話していこうと思います
フェイスブックページ https://www.facebook.com/kids.POWERS
こんにちは

先日、学生観光振興プロジェクトの報告会に参加してきました

一人一人が向上心を持って活動をしている姿や、熱い想い等がひしひしと伝わってきました

僕たちはまだ無限のつぼみです

信じ続けて進みましょう

どんな花も咲かすでしょう

私も、負けないように頑張ります


さて、本日の本題に入っていきますが、その前に前回の記事をご覧になっていない方はご覧になってからこの記事を読んでください

テーマは「うちの子って褒めるところがないってほんと?」についてです

まず、皆さんは子どもをどういう目で見ていますか


子どもは子どもだと思って接しすぎていませんか?
子どもも一人の人間です


「勉強しない、家の手伝いをしない、忘れ物が多いとか、うちの子って褒めるところないんですよ~」なんてそんな言葉をよく聞きます

褒めるところが見つからないというのは、大人が勝手に「ここまでできないとほめられない」と、心のストライクゾーンを狭べているだけではないでしょうか

みなさんは、子どもを思う気持ちが強すぎて、しっかりしなきゃなんて思い過ぎなのかもしれません

もっと無駄に力を入れないでください

「一緒に遊ぶ友達がこんなにいるのは、優しいからだよね」「毎日よく寝て食べているんだから、健康ってことよね。大したもんよ」など、そんな風に広く視点を変えてみてもいいかもしれません

つまり、子どもは自分なりに頑張っているのです

その、頑張りを親の基準に満たないからと押し付けるようなことはしないで欲しいということです

子どもの教育はその子のダメなところ、いいところを見抜いて、見抜いて、我慢をする、見守る能力も必要です

悪いところは子どもが自分自身で気づかせるようにすることも大事です


しかし、褒められないという人の中には褒めることに対して否定的な人がいます

褒め言葉を言うなんて自分らしくない、褒められると落ち着かないと。多くの場合は、自分が褒められずに育ってきた人です

「褒められなかったからこそ頑張れた」とむしろ褒めない育児を肯定しています

しかし、虐待が連鎖するように、褒められない成育歴も連鎖します

たとえ親が今幸せになれたとしても、こどもが同じように幸せに生きられるとは限りませんよ
 どこかで断ち切ってください
どこかで断ち切ってください
そこまで、重い理由がなくても、親自身の精神状態や身体状態が良くない場合、余裕がなくなってしまって、我が子のいいところが見えなくなってしまいます

子どもの悪いところしか見えないと思ったら、それは親自身のSOSサインです

家族や実家にSOSを出して助けをもらったり、学校カウンセラーに相談してみてらいいかもしれません

そして、頑張っている自分をちゃんと褒めてあげてください


次回は、新しい豆知識に入っていきます

子どものしつけについて中心にしてお話していこうと思います

フェイスブックページ https://www.facebook.com/kids.POWERS
2012年03月25日
こどものやる気アップ part26
みなさん!
こんにちは!
代表の狩俣です
久しぶりの更新です
最近は、気温の変化が大きいですよね
気温が最高25度以上になる時もあれば、最高17度になることもあります
みなさん!
気温の変化に体調を崩さないように気をつけてくださいね

今日は、前回の「こどもをどう褒める?」
について6つのほめ方のうち3つを紹介しました
前回の記事をご覧になっていいない方は是非、ご覧になってみてください
今日は、残りの3つのほめ方についてお話していきたいと思います
④時々褒める⇔いつも褒める
悲しいかな、いつも褒め続けているとありがたみはなくなってしまうものです。年齢が上がるほど、タイミングを見計らってほめてあげることも必要かもしれません。本当にその子が努力をした時にちゃんと認めてあげればいいんですよ

⑤派手にほめる⇔冷静に褒める
幼少期など小さい時は拍手喝采されるのを喜びますが、思春期以降は冷静な褒め言葉の方が受け入れやすいです
「以前よりはこういうところが伸びたね 」「あなたならこういうことができるんじゃない
」「あなたならこういうことができるんじゃない
 」等と客観的なほめ方が成長の糧になるんです
」等と客観的なほめ方が成長の糧になるんです
⑥言葉以外のメッセージで伝える
子どもが描いてくれた絵を額にいれて飾っておくこと、子どもからのプレゼントを大事にとっておく、お弁当に励ましのメッセージを添える等と、「私はあなたを大事に思っています。大事な存在」と伝える方法はいろいろです


みなさんのお子さん、または学生の方であれば小さい兄弟やいとこがいらっしゃる方は子どもにどういうふうに声をかけてあげていますか?
是非、自分の言葉はその子にとってプラスになっているのかどうかを考えてみてください
次回は、お子さんが勉強しない、朝なかなか起きない、家の手伝いもしない、忘れ物もいっぱい・・・・・・「うちの子って・・・褒めるところ全然ないじゃない」なんていう方もいます。しかし、本当にそうでしょうか・・・?
次回は、「うちの子って褒めるところがないって本当?」についてお話していきます
お楽しみに~('∀`)
フェイスブックページもあります!!
https://www.facebook.com/kids.POWERS
こんにちは!
代表の狩俣です

久しぶりの更新です

最近は、気温の変化が大きいですよね

気温が最高25度以上になる時もあれば、最高17度になることもあります

みなさん!
気温の変化に体調を崩さないように気をつけてくださいね


今日は、前回の「こどもをどう褒める?」
について6つのほめ方のうち3つを紹介しました

前回の記事をご覧になっていいない方は是非、ご覧になってみてください

今日は、残りの3つのほめ方についてお話していきたいと思います

④時々褒める⇔いつも褒める
悲しいかな、いつも褒め続けているとありがたみはなくなってしまうものです。年齢が上がるほど、タイミングを見計らってほめてあげることも必要かもしれません。本当にその子が努力をした時にちゃんと認めてあげればいいんですよ


⑤派手にほめる⇔冷静に褒める
幼少期など小さい時は拍手喝采されるのを喜びますが、思春期以降は冷静な褒め言葉の方が受け入れやすいです

「以前よりはこういうところが伸びたね
 」「あなたならこういうことができるんじゃない
」「あなたならこういうことができるんじゃない
 」等と客観的なほめ方が成長の糧になるんです
」等と客観的なほめ方が成長の糧になるんです
⑥言葉以外のメッセージで伝える
子どもが描いてくれた絵を額にいれて飾っておくこと、子どもからのプレゼントを大事にとっておく、お弁当に励ましのメッセージを添える等と、「私はあなたを大事に思っています。大事な存在」と伝える方法はいろいろです



みなさんのお子さん、または学生の方であれば小さい兄弟やいとこがいらっしゃる方は子どもにどういうふうに声をかけてあげていますか?

是非、自分の言葉はその子にとってプラスになっているのかどうかを考えてみてください

次回は、お子さんが勉強しない、朝なかなか起きない、家の手伝いもしない、忘れ物もいっぱい・・・・・・「うちの子って・・・褒めるところ全然ないじゃない」なんていう方もいます。しかし、本当にそうでしょうか・・・?
次回は、「うちの子って褒めるところがないって本当?」についてお話していきます

お楽しみに~('∀`)
フェイスブックページもあります!!
https://www.facebook.com/kids.POWERS
2012年02月24日
こどものやる気アップ part25
みなさん!
こんにちは
代表の狩俣です
今日は「こどものやる気アップ」についてお話していこうと思います
前回の内容は「褒めることの落とし穴」についてお話しました
忘れてしまった方はもう一度ご覧ください
まだ、ご覧になっていない方は一度目を通してこの記事をご覧になってください

今回のテーマは「こどもをどう褒める?」です
子どもを褒める時、具体的にどんなほめ方があるのでしょうか
しっかり考えると、実に様々なバリエーションがあります
では、どのようなほめ方があるのかご紹介しましょう

①直接褒める⇔間接的に褒める
②全体を褒める⇔部分を褒める
③絶対的に褒める⇔相対的に褒める
④ときどき褒める⇔いつも褒める
⑤派手に褒める⇔冷静に褒める
⑥コトバ以外のメッセージで伝える

この6つがあります
それでは一つ一つ見ていきましょう
①直接褒める⇔間接的に褒める
お母さんが「がんばったね」「嬉しい」というのが、直接褒めるということです
間接的に褒めるというのは「学校の先生もあなたの努力をほめていたよ」と伝えることです
直接褒められることも嬉しいことですが、間接的に褒められることで二重の褒め言葉を受け取ることになります

②全体を褒める⇔部分を褒める
例えば、「あの子素敵ね」という表現は全体を褒めることですが、「あの子の髪型はすてきね」と部分だけ取り出して褒めると「ほかは好きではない」という印象を与えかねません
特に、優れた部分をとりだして褒めることは構わないと思いますが、言葉のニュアンスに気をつけたいものです
「あなたは勉強ができるね」と言われるのと「あなたは勉強はできるね」というのでは、嬉しさがちがいます
それ以外がけなされていると感じさせないようにしたいものです

③絶対的に褒める⇔相対的に褒める
相対的に褒めるというのは、誰かと比較して褒めることです
例えば、「○○くんよりはいいよね」というほめ方は避けたいものです
「えこひいき」「ひがみ」などゆがんだ人間関係になりかねません

「あなたは人に優しくできるところがいいよね」とその子その子の良さを認め、絶対的な存在として褒めてあげたいものです

僕も、よく子どもたちと遊んだりするのですが、少し言葉の使い方に気をつけていこうと思います
子どもも人の言葉をしっかり聞いているんですよ
次回はつづきの残り3つのほめ方についてお話していきます
次回をお楽しみに~
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
こんにちは

代表の狩俣です

今日は「こどものやる気アップ」についてお話していこうと思います

前回の内容は「褒めることの落とし穴」についてお話しました

忘れてしまった方はもう一度ご覧ください

まだ、ご覧になっていない方は一度目を通してこの記事をご覧になってください


今回のテーマは「こどもをどう褒める?」です

子どもを褒める時、具体的にどんなほめ方があるのでしょうか

しっかり考えると、実に様々なバリエーションがあります

では、どのようなほめ方があるのかご紹介しましょう


①直接褒める⇔間接的に褒める
②全体を褒める⇔部分を褒める
③絶対的に褒める⇔相対的に褒める
④ときどき褒める⇔いつも褒める
⑤派手に褒める⇔冷静に褒める
⑥コトバ以外のメッセージで伝える

この6つがあります

それでは一つ一つ見ていきましょう

①直接褒める⇔間接的に褒める
お母さんが「がんばったね」「嬉しい」というのが、直接褒めるということです

間接的に褒めるというのは「学校の先生もあなたの努力をほめていたよ」と伝えることです

直接褒められることも嬉しいことですが、間接的に褒められることで二重の褒め言葉を受け取ることになります


②全体を褒める⇔部分を褒める
例えば、「あの子素敵ね」という表現は全体を褒めることですが、「あの子の髪型はすてきね」と部分だけ取り出して褒めると「ほかは好きではない」という印象を与えかねません

特に、優れた部分をとりだして褒めることは構わないと思いますが、言葉のニュアンスに気をつけたいものです

「あなたは勉強ができるね」と言われるのと「あなたは勉強はできるね」というのでは、嬉しさがちがいます

それ以外がけなされていると感じさせないようにしたいものです


③絶対的に褒める⇔相対的に褒める
相対的に褒めるというのは、誰かと比較して褒めることです

例えば、「○○くんよりはいいよね」というほめ方は避けたいものです

「えこひいき」「ひがみ」などゆがんだ人間関係になりかねません


「あなたは人に優しくできるところがいいよね」とその子その子の良さを認め、絶対的な存在として褒めてあげたいものです


僕も、よく子どもたちと遊んだりするのですが、少し言葉の使い方に気をつけていこうと思います

子どもも人の言葉をしっかり聞いているんですよ

次回はつづきの残り3つのほめ方についてお話していきます

次回をお楽しみに~

参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
2012年02月17日
こどものやる気アップ part24
みなさん!
こんにちは
今日は子育て豆知識についてお話していこうと思います
前回は「褒めることの欠陥はどうなるのか」についてお話しました
まだ、ご覧になっていない方は今すぐ、前回の記事をご覧ください
今回のテーマは「褒めることの落とし穴」についてお話していきます
この記事をご覧になっている方で学生やお母さんの方もいらっしゃるかもしれませんが、お子さんをお持ちの方がこの記事をご覧になっていただいていると思います

僕が、褒めることは大事だと今まで言ってきましたが、だだただ子どもを褒めるだけでは子どもも馬鹿ではないのですからその褒められ方で考え方も変わってきますし、その褒めている人の気持ちも感じることもできます
そこで、褒める時にTPOに気をつけてほしいです
つまり、「時間(time)、場所(place)、場合(occasion)」に気を付けて、子どもを褒める、叱ることです
一見褒めているようで、子どもの心のエネルギーを逆に吸い取ってしまっているコトバもあるということを知っておいてください
それは、3つあります
一つ目は、「一番だから」「勝ったから」褒めるということ
二つ目は、「たしなめるべき場面で褒める」ことです
三つ目は、「親が何か見返りを求めて」褒めることです
一つ目のことについてです
親が「あなたは一番にならなきゃダメよ」「勝たなきゃダメ」という言葉をかけると、そこには結果主義が見えます
そうやって小さい時に育てられて生きた子は、「一番、一番」というこだわりがひ非常に強くなり、そこに至る過程を楽しめなくなる、手段を選ばなくなるということになりかねません


結果を出せても、次はもっといい結果を取らなくちゃとプレッシャーが重くのしかかります
二つ目についてです
親が「褒めて育てなくっちゃ」と思い込むあまりにたしなめたり、叱ったりする場面で褒めてしまうということです
例えば、まだ2,3歳のお子さんではいつでもどこでも「自分で」やりたがります
それを常に「ダメでしょ、できないでしょ」というのではなく「頑張ってみて」とやらせてあげるのはいいですが、それはあくまで家庭内でのことです。つまり、場所やタイミングが今のこの子にとって必要なものなのか、またそれが周りに迷惑にならないのかを考えてください
あえて、周りが見ている中で叱ることも必要な場面、タイミングもあると思っています

「ここは込んでいるからお家に帰ってからね」と子どもに教えることも親のやることだということです
それが、なければ子どもから社会性を学ぶチャンスを奪い取る結果になってしまいます

3つめについてです
親が「褒めることで、子どもを意図的にあやつっちゃお」という目論見から出る褒め言葉は子どもの心に確実に不信感を抱かせます
小さい頃はそれで、通用するでしょう
しかし、成長するにつれて子どもは馬鹿じゃないですから「うまいこと言って、またおもいどうりにしてやがるよこの人は」なんて見抜くようになります

その反動で家庭内暴力や反社会的な行動といった形で表れることが少なくないです

つまり、「褒める」とは「相手を想っている」という気持ちの表現方法のひとつなんです
親の自己愛ではなく、他者としてしっかり愛する時子どもたちの心にしっかり届き、エネルギーを送ることになるのです
熱意です
その言葉はきっとその子が何歳になっても心のよりどころ「おふくろのコトバ・名言」となって自信の源になるに違いありません
次回は「ほめ方は一つじゃない」です
こどものほめ方の種類をお教えします!
参考文献:「我が子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
こんにちは

今日は子育て豆知識についてお話していこうと思います

前回は「褒めることの欠陥はどうなるのか」についてお話しました

まだ、ご覧になっていない方は今すぐ、前回の記事をご覧ください

今回のテーマは「褒めることの落とし穴」についてお話していきます

この記事をご覧になっている方で学生やお母さんの方もいらっしゃるかもしれませんが、お子さんをお持ちの方がこの記事をご覧になっていただいていると思います


僕が、褒めることは大事だと今まで言ってきましたが、だだただ子どもを褒めるだけでは子どもも馬鹿ではないのですからその褒められ方で考え方も変わってきますし、その褒めている人の気持ちも感じることもできます

そこで、褒める時にTPOに気をつけてほしいです

つまり、「時間(time)、場所(place)、場合(occasion)」に気を付けて、子どもを褒める、叱ることです

一見褒めているようで、子どもの心のエネルギーを逆に吸い取ってしまっているコトバもあるということを知っておいてください

それは、3つあります

一つ目は、「一番だから」「勝ったから」褒めるということ
二つ目は、「たしなめるべき場面で褒める」ことです
三つ目は、「親が何か見返りを求めて」褒めることです
一つ目のことについてです

親が「あなたは一番にならなきゃダメよ」「勝たなきゃダメ」という言葉をかけると、そこには結果主義が見えます

そうやって小さい時に育てられて生きた子は、「一番、一番」というこだわりがひ非常に強くなり、そこに至る過程を楽しめなくなる、手段を選ばなくなるということになりかねません



結果を出せても、次はもっといい結果を取らなくちゃとプレッシャーが重くのしかかります

二つ目についてです

親が「褒めて育てなくっちゃ」と思い込むあまりにたしなめたり、叱ったりする場面で褒めてしまうということです

例えば、まだ2,3歳のお子さんではいつでもどこでも「自分で」やりたがります

それを常に「ダメでしょ、できないでしょ」というのではなく「頑張ってみて」とやらせてあげるのはいいですが、それはあくまで家庭内でのことです。つまり、場所やタイミングが今のこの子にとって必要なものなのか、またそれが周りに迷惑にならないのかを考えてください

あえて、周りが見ている中で叱ることも必要な場面、タイミングもあると思っています


「ここは込んでいるからお家に帰ってからね」と子どもに教えることも親のやることだということです

それが、なければ子どもから社会性を学ぶチャンスを奪い取る結果になってしまいます


3つめについてです

親が「褒めることで、子どもを意図的にあやつっちゃお」という目論見から出る褒め言葉は子どもの心に確実に不信感を抱かせます

小さい頃はそれで、通用するでしょう

しかし、成長するにつれて子どもは馬鹿じゃないですから「うまいこと言って、またおもいどうりにしてやがるよこの人は」なんて見抜くようになります


その反動で家庭内暴力や反社会的な行動といった形で表れることが少なくないです


つまり、「褒める」とは「相手を想っている」という気持ちの表現方法のひとつなんです

親の自己愛ではなく、他者としてしっかり愛する時子どもたちの心にしっかり届き、エネルギーを送ることになるのです

熱意です

その言葉はきっとその子が何歳になっても心のよりどころ「おふくろのコトバ・名言」となって自信の源になるに違いありません

次回は「ほめ方は一つじゃない」です

こどものほめ方の種類をお教えします!
参考文献:「我が子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
2012年02月13日
こどものやる気アップ part23
みなさん!
こんにちは
POWERS代表の狩俣です
最近まで、一週間ぐらいダウンしていました
かなりの高熱とせきで体がだるく、全く動けませんでした
それによって失った時間のロスがあまりにも大きく感じている今日この頃です
病気になると、お金もかかるし、時間もとられるし、心が沈むしで良いこと何もないです
やっぱり健康第一ですね
皆さんも、ビタミンCをとって風邪に負けないようにしていきましょう

さて、前回で「行動をほめる」「存在をほめる」という2つの褒めるポイントを教えましたが、今回は「褒めることの欠落の問題点」についてお話していこうと思います
2つの中で、一番不足してはいけないことが「存在を褒める」ことです
昔と変わって現代のここ十年ほどの少年事件を見ていると加害者の少年たちに人間として大切なものが欠落していると感じます

その一つは「社会的能力」です
お言葉の通り、社会で生きていくための能力です。
自分の気持ちを伝える、人と仲良くする、結果を予測して行動する、その場の状況を適切に判断するetc。そういった知恵、技能が未熟すぎるのです
もう一つは「情緒的能力」。
つまり、心をコントロールする力です
思いやり、やさしさ、豊かな感情を持って人の悲しみetcを感じる、そして受け止めてあげる力も足りていません
この二つの能力は「存在を褒める」言葉の中で育まれるものだと考えます
「安心して」「大好きだよ」「生まれてきてくれてママほんと嬉しい、ありがとう 」という思いやりに包まれて育つからこそ他者を思いやる気持ちを育てることができるわけですよ
」という思いやりに包まれて育つからこそ他者を思いやる気持ちを育てることができるわけですよ

みなさんのお母さんも皆さんを思いやりで包んできたからこそ、今あなたは思いやりや優しさにあふれた人になっているに違いありません
感謝、感謝

では、この事をされていない子または不足した子はどうなるのか
将来が不安ですね
幼児期~児童期間に褒めることがベストですが、それをしなくてもその時期では問題は表面化しません
問題に現れてくるのは・・・中学生以降です
思春期の頃になると、彼らの心には数年もかけて積み上げられてきたバツが並び、マルはほとんどない状態です
そのため、自分を価値のない人間だと見放し、自分の心と体を粗末に扱います
ましてや、他人を思いやることなどもってのほかです

「そういうことしてはダメ」といってもかたくなな心はもう聞きません
自分も人も信じていないわけですから、怒られると憎しみを抱くだけです
だからこそ、子どもが小さい幼いときにしっかりとたくさんマルをつけてあげてください

「じゃあ、あとになって気づいてもあとのまつりじゃない」と思った方、思春期になっても遅すぎることはありません
時間はかなりかかりますが、「あなたが居て良かった」と愛情を強く伝え続けてください。きっと届きます
次回は、褒めることは褒めることでも気をつけて褒めてほしいです。褒めるタイミングというのも大事になってきます。
次回のテーマは「褒めるときに気をつけること」です
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
こんにちは

POWERS代表の狩俣です

最近まで、一週間ぐらいダウンしていました

かなりの高熱とせきで体がだるく、全く動けませんでした

それによって失った時間のロスがあまりにも大きく感じている今日この頃です

病気になると、お金もかかるし、時間もとられるし、心が沈むしで良いこと何もないです

やっぱり健康第一ですね

皆さんも、ビタミンCをとって風邪に負けないようにしていきましょう


さて、前回で「行動をほめる」「存在をほめる」という2つの褒めるポイントを教えましたが、今回は「褒めることの欠落の問題点」についてお話していこうと思います

2つの中で、一番不足してはいけないことが「存在を褒める」ことです

昔と変わって現代のここ十年ほどの少年事件を見ていると加害者の少年たちに人間として大切なものが欠落していると感じます


その一つは「社会的能力」です

お言葉の通り、社会で生きていくための能力です。
自分の気持ちを伝える、人と仲良くする、結果を予測して行動する、その場の状況を適切に判断するetc。そういった知恵、技能が未熟すぎるのです

もう一つは「情緒的能力」。
つまり、心をコントロールする力です

思いやり、やさしさ、豊かな感情を持って人の悲しみetcを感じる、そして受け止めてあげる力も足りていません

この二つの能力は「存在を褒める」言葉の中で育まれるものだと考えます

「安心して」「大好きだよ」「生まれてきてくれてママほんと嬉しい、ありがとう
 」という思いやりに包まれて育つからこそ他者を思いやる気持ちを育てることができるわけですよ
」という思いやりに包まれて育つからこそ他者を思いやる気持ちを育てることができるわけですよ

みなさんのお母さんも皆さんを思いやりで包んできたからこそ、今あなたは思いやりや優しさにあふれた人になっているに違いありません

感謝、感謝


では、この事をされていない子または不足した子はどうなるのか

将来が不安ですね

幼児期~児童期間に褒めることがベストですが、それをしなくてもその時期では問題は表面化しません

問題に現れてくるのは・・・中学生以降です

思春期の頃になると、彼らの心には数年もかけて積み上げられてきたバツが並び、マルはほとんどない状態です

そのため、自分を価値のない人間だと見放し、自分の心と体を粗末に扱います

ましてや、他人を思いやることなどもってのほかです


「そういうことしてはダメ」といってもかたくなな心はもう聞きません

自分も人も信じていないわけですから、怒られると憎しみを抱くだけです

だからこそ、子どもが小さい幼いときにしっかりとたくさんマルをつけてあげてください


「じゃあ、あとになって気づいてもあとのまつりじゃない」と思った方、思春期になっても遅すぎることはありません

時間はかなりかかりますが、「あなたが居て良かった」と愛情を強く伝え続けてください。きっと届きます

次回は、褒めることは褒めることでも気をつけて褒めてほしいです。褒めるタイミングというのも大事になってきます。
次回のテーマは「褒めるときに気をつけること」です
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
2012年02月08日
POWERS勉強会 ~もっと高見へ、もっと己を磨け~
みなさん!
こんにちは
代表の狩俣(カーリィー)です
最近テレビでもたくさん言われてますが、インフルエンザが全国的に広まってきているそうです
とくにA香港型が広がってきているそうです
皆さんも風邪やインフルエンザには気をつけてくださいね
うがい手洗いはもちろん、さらに温かい恰好でお出かけしてください

さて、先日の2月1日にPOWERS勉強会がありました
今回は私狩俣がプレゼンテーションをしました
テーマは「決断力」です
やはり、誰もが自分に足りない能力として一番に挙げているのがこの「決断力」なんですね

決断と言うと毎日何かしら誰でも決断の連続で生活しているものです
誰しも、これまでの人生で「大きな決断を下す」ことに立たされた経験があると思います
プライベートで言えば、学生時代の「志望校を選ぶ」「入るサークルを決める」といった決断に始まり、「家を買う」など、多くの決断をしてきたと思います
仕事で言っても、「M&Aする企業」「転職をする」など、決断すべきことは数多くあります
しかし、難しい決断になればなるほど、考えることが大きすぎてよくわからなくなり、感情に流されてしまって、正しい判断を下せなくなりがちです
直感でパッと決めてしまった結果、後になってから「あぁ、失敗した」と悔やんだことはないでしょうか

自分で決断していてもなぜか不安になって他の人の意見の方に流されてしまうような事があると思います

辞書で「決断力」を調べると、「自分自身の判断・責任で決断する能力。」だそうです
つまり逆にいえば「決断力不足」=「優柔不断」なわけです
優柔不断ということはつまり、決断が出来ない人の多くは、「自分の思い」がはっきりしていない人なのです。
優柔不断な人は、実は「決断力」に問題があるのではなくて、「そもそも、自分はどうしたいのか」がはっきりとしないために、目の前にある出来事が「良い」「悪い」のか判断できないわけです。
実際、考えることが大きくなればなるほど、「自分がどうしたいのか」がわからなくなりますよね。例えば投資先を考える時、「自分の人生をトータルで考えた時、自分は本当はどういうことを望んでいるのか?」と改まって考えても、なかなか「これ」といった答えを出すのは難しいと思います
決断をするためには、まずは「自分がどうしたいのかをはっきりさせる」こと
自分の夢や目標を持つことが一番決断力が付くことなんです
っとまあこんな感じでお話させていただきました
今、ご覧になっているあなたに少しでも勉強になってくれれば幸いです!
次回の勉強会の記事をおたのしみに
こんにちは

代表の狩俣(カーリィー)です

最近テレビでもたくさん言われてますが、インフルエンザが全国的に広まってきているそうです

とくにA香港型が広がってきているそうです

皆さんも風邪やインフルエンザには気をつけてくださいね

うがい手洗いはもちろん、さらに温かい恰好でお出かけしてください


さて、先日の2月1日にPOWERS勉強会がありました

今回は私狩俣がプレゼンテーションをしました

テーマは「決断力」です

やはり、誰もが自分に足りない能力として一番に挙げているのがこの「決断力」なんですね

決断と言うと毎日何かしら誰でも決断の連続で生活しているものです

誰しも、これまでの人生で「大きな決断を下す」ことに立たされた経験があると思います

プライベートで言えば、学生時代の「志望校を選ぶ」「入るサークルを決める」といった決断に始まり、「家を買う」など、多くの決断をしてきたと思います

仕事で言っても、「M&Aする企業」「転職をする」など、決断すべきことは数多くあります

しかし、難しい決断になればなるほど、考えることが大きすぎてよくわからなくなり、感情に流されてしまって、正しい判断を下せなくなりがちです

直感でパッと決めてしまった結果、後になってから「あぁ、失敗した」と悔やんだことはないでしょうか


自分で決断していてもなぜか不安になって他の人の意見の方に流されてしまうような事があると思います

辞書で「決断力」を調べると、「自分自身の判断・責任で決断する能力。」だそうです

つまり逆にいえば「決断力不足」=「優柔不断」なわけです

優柔不断ということはつまり、決断が出来ない人の多くは、「自分の思い」がはっきりしていない人なのです。
優柔不断な人は、実は「決断力」に問題があるのではなくて、「そもそも、自分はどうしたいのか」がはっきりとしないために、目の前にある出来事が「良い」「悪い」のか判断できないわけです。
実際、考えることが大きくなればなるほど、「自分がどうしたいのか」がわからなくなりますよね。例えば投資先を考える時、「自分の人生をトータルで考えた時、自分は本当はどういうことを望んでいるのか?」と改まって考えても、なかなか「これ」といった答えを出すのは難しいと思います

決断をするためには、まずは「自分がどうしたいのかをはっきりさせる」こと

自分の夢や目標を持つことが一番決断力が付くことなんです

っとまあこんな感じでお話させていただきました

今、ご覧になっているあなたに少しでも勉強になってくれれば幸いです!
次回の勉強会の記事をおたのしみに

2012年02月04日
こどものやる気アップ part22
こんにちは!
代表の狩俣です
みなさん僕のことを「カーリィー」とよんでくださいね
ただ、前のバイトでカーリィーと呼ばれていただけなんですけどね
カービィーじゃないですよ

今日はこどものやる気アップの前回の続きですね
前回の続きを忘れた方は前に戻って読んでからこの記事をもう一度読み返してください
今回は「こどもをどんなふうに褒めたら良いのか!」です
前回の記事をご覧になってみたらわかると思いますが、キーワードとして子どもにマルをつけてあげる事がキーワードでした
その中で、こどもにマルをつける際にこどもを「褒めること」つまり、こどもを甘やかすのでも叱る事でもなく「こどもを認める」ことが大事だと教えました
かなり端折っているのですが、つかめましたでしょうか


では、本題に入っていきます
どんなふうにこどもを褒めたらいいか
それはズバリ言うと2つあります
つまり、褒める点は二つの事のみ
1つ目は「行動」をほめる
2つ目は「存在」をほめる
たったこれだけ なんです!
なんです!

「たったこれだけなら私は苦労しないわよ」とおっしゃっているそこのお兄さん、お姉さん、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃん
これだけがなかなかできていない、していない保護者の方が多いんですよ
一つ目の「行動」をほめることについてちょっと説明すると、その子がやり遂げてたこと、誰かにしてあげたこと、さらに努力したことに対して「それは良かった」「頑張ったね 」と認めて、マルをつけてあげるということです
」と認めて、マルをつけてあげるということです

二つ目の「存在」をほめることを説明すると、特に何かをしなくても褒められる、生きているだけで褒められるというものです
「はぁ 」と思った方、もうちょっと詳しく説明しましょう
」と思った方、もうちょっと詳しく説明しましょう
赤ちゃんがそうですね
赤ちゃんは親の顔をじっと見るだけで「賢いね」と褒められたり、ウンチをするだけで「お利口だね」と喜ばれる
「あなたが居てくれるだけで嬉しい。ありがとう」なんて言ってくれる人は家族以外にはいません
特に2つの中で大事なのが、「存在」を褒めることです

まとめてみましょう
行動をほめる
⇒行動をほめられることで意欲がわき、次はもっとがんばろうと思う。自分がしている行動が正しいと自覚し「これからも続けていこう」と自覚する。
存在をほめる
「優しい子だね」「あなたの笑顔が好き」etc
⇒自己肯定感が育ち、自分は価値ある存在だと思える。その過程で、他者の価値も自然にわかるようになる。いきることが楽しいと思えて、人生に充足感を味わえる。
たったこれだけをすることで、つまりマルをつけてあげることで、こども達は心のエネルギーがたまっていくんです
次回は「その褒める2つの要素の欠落した場合」についてお話していきます
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
代表の狩俣です

みなさん僕のことを「カーリィー」とよんでくださいね

ただ、前のバイトでカーリィーと呼ばれていただけなんですけどね

カービィーじゃないですよ


今日はこどものやる気アップの前回の続きですね

前回の続きを忘れた方は前に戻って読んでからこの記事をもう一度読み返してください

今回は「こどもをどんなふうに褒めたら良いのか!」です

前回の記事をご覧になってみたらわかると思いますが、キーワードとして子どもにマルをつけてあげる事がキーワードでした

その中で、こどもにマルをつける際にこどもを「褒めること」つまり、こどもを甘やかすのでも叱る事でもなく「こどもを認める」ことが大事だと教えました

かなり端折っているのですが、つかめましたでしょうか



では、本題に入っていきます

どんなふうにこどもを褒めたらいいか

それはズバリ言うと2つあります

つまり、褒める点は二つの事のみ

1つ目は「行動」をほめる

2つ目は「存在」をほめる

たったこれだけ
 なんです!
なんです!
「たったこれだけなら私は苦労しないわよ」とおっしゃっているそこのお兄さん、お姉さん、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃん

これだけがなかなかできていない、していない保護者の方が多いんですよ

一つ目の「行動」をほめることについてちょっと説明すると、その子がやり遂げてたこと、誰かにしてあげたこと、さらに努力したことに対して「それは良かった」「頑張ったね
 」と認めて、マルをつけてあげるということです
」と認めて、マルをつけてあげるということです

二つ目の「存在」をほめることを説明すると、特に何かをしなくても褒められる、生きているだけで褒められるというものです

「はぁ
 」と思った方、もうちょっと詳しく説明しましょう
」と思った方、もうちょっと詳しく説明しましょう
赤ちゃんがそうですね

赤ちゃんは親の顔をじっと見るだけで「賢いね」と褒められたり、ウンチをするだけで「お利口だね」と喜ばれる

「あなたが居てくれるだけで嬉しい。ありがとう」なんて言ってくれる人は家族以外にはいません

特に2つの中で大事なのが、「存在」を褒めることです


まとめてみましょう

行動をほめる

⇒行動をほめられることで意欲がわき、次はもっとがんばろうと思う。自分がしている行動が正しいと自覚し「これからも続けていこう」と自覚する。
存在をほめる

「優しい子だね」「あなたの笑顔が好き」etc
⇒自己肯定感が育ち、自分は価値ある存在だと思える。その過程で、他者の価値も自然にわかるようになる。いきることが楽しいと思えて、人生に充足感を味わえる。
たったこれだけをすることで、つまりマルをつけてあげることで、こども達は心のエネルギーがたまっていくんです

次回は「その褒める2つの要素の欠落した場合」についてお話していきます

参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
2012年01月27日
POWERS勉強会 ~もっと高見へ、もっと己を磨け~
こんにちは!
POWERS代表の狩俣です
最近は日照時間が少なくてちょっと気分も沈みがちですよね
でも、POWERSの気持ちは熱いですよ
先日の1月25日にPOWERS勉強会がありました
今回は勉強会のプレゼンの内容とと少しずれてしまう時間もありましたが、結構盛り上がりました
今回のプレゼンは希玲さん
テーマは「続ける技術」
シンプルすぎだろ
ってかそのまんまやんか
逆にそれの方がかっこよく見えますかね

5時間をかけてプレゼンを作ってきたと言う希玲さん
白熱してます

この言葉は有名ですね
希玲さんはいつもよりは大きな声でこの言葉を言ってました
「継続は力」、「数は力」ですね

すごいわかりやすく発表していただきました
でも、なんか質問をしていくうちに「コミュニケーション」の話にそれていってしまいました
でも、最終的に戻ったので大丈夫でしたよ
次に一分間スピーチをしました
一分間という時間でいかに相手にわかりやすく、面白く発表できるか
しかも、即興なのでいかに早く頭の中で話をまとめられるかがポイントです
今回のテーマは「今日一日の出来事(ハプニング) 」でした!
」でした!
次回は僕が誰もが一番自分に足りないと感じている能力「決断力」について僕なりにプレゼンしていきます
では、また!
POWERS代表の狩俣です

最近は日照時間が少なくてちょっと気分も沈みがちですよね

でも、POWERSの気持ちは熱いですよ

先日の1月25日にPOWERS勉強会がありました

今回は勉強会のプレゼンの内容とと少しずれてしまう時間もありましたが、結構盛り上がりました

今回のプレゼンは希玲さん

テーマは「続ける技術」
シンプルすぎだろ

ってかそのまんまやんか

逆にそれの方がかっこよく見えますかね

5時間をかけてプレゼンを作ってきたと言う希玲さん

白熱してます


この言葉は有名ですね

希玲さんはいつもよりは大きな声でこの言葉を言ってました

「継続は力」、「数は力」ですね


すごいわかりやすく発表していただきました

でも、なんか質問をしていくうちに「コミュニケーション」の話にそれていってしまいました

でも、最終的に戻ったので大丈夫でしたよ

次に一分間スピーチをしました

一分間という時間でいかに相手にわかりやすく、面白く発表できるか

しかも、即興なのでいかに早く頭の中で話をまとめられるかがポイントです

今回のテーマは「今日一日の出来事(ハプニング)
 」でした!
」でした!次回は僕が誰もが一番自分に足りないと感じている能力「決断力」について僕なりにプレゼンしていきます

では、また!
2012年01月24日
こどものやる気アップ part21
こんにちは!
POWERS代表の狩俣です
今回も、こどもの成長がうかがえる感動のストーリーをお届けしたいと思います
ある記事に載っていたものなんですが、かなり素晴らしいものだと思ったので載せてみました

もうすぐ2才になるあずちゃん。このごろ家でのいたずらぶりがあまりにもひどい。ベランダから、おもちゃを次々に投げたり、部屋のすみっこでわざとおしっこをしたり…。いくら叱ってもまたやるので、ママはもう気が変になりそう。1ヶ月前に断乳に挑戦してから、こんな調子です。結局断乳はとりやめたのですが、やはりストレスになったのでは?とママは重い気持ちでした。
ところが、よくよくあずちゃんの思いをたぐっていくと、その本音は全く違うところにあることがわかったのです。ママの想像とはまったく逆で、断乳がうまくいかなかったこと、りっぱなお姉さんになりそこなったくやしさが、あずちゃんのいらだちの原因だったのです。その思いに気づいたママは、断乳に再挑戦。みごと乗り越えたあずちゃんは、すっかり落ちつき、グンとお姉さんらしい、自信に満ちた顔つきになりました。

こども達は自分でいろいろ成長して自分を高めていこうと必死です
自分で、いろいろ挑戦していこうとしていることがわかります
この記事を読んでいただいているあなたも、いろいろ挑戦していきましょう
感動の話はこのぐらいにして、今日のテーマは「こどもの心にたくさんのマルをつけよう!」です
話に入る前にまず、最初に質問に答えてこどもがの事をどれだけ分かっているかの確認のテストをしたいと思います!
幼稚園の先生や、保育園の先生や小学校の先生などを目指している学生さんや、現役で教員をしていらっしゃる方にも是非、このテストをお勧めします

「子どものいいとこリスト」
Q1.うちの子は____が得意です!
Q2.うちの子は____ができます!
Q3.うちの子はいつも____して偉い!
Q4.うちの子は____と人に褒められます!
Q5.うちの子は____をするのが上手です!
Q6.うちの子のいいところはズバリ____です!
Q7.私はうちの子を____と自慢できます!
Q8.私はうちの子の____が大好きです!
Q9.うちの子の____なところは夫に似て良かった!
Q10.うちの子の_____なところは私に似て良かった!
さて、この質問にさらっとこたえられたでしょうか?
さらっと答えられたら、あなたはこどもの事を良く見ていて、良く分かっている、つまりこどもの「いいところ探し」をしっかりしているということです
分かっているけど、書けない人は口に出す習慣がなかったのかもしれません
こどもにどんどん口に出してあげてほしいと思います!
1つ名言を残しておきましょう
「口に出さずは相手に気持ちは伝わらない!」 by suguru karimata

結構前に、こどものセルフイメージを高めることが大切と言うことでたくさんのマルをつけてあげようと話しました
今回も、こどもをほめることについてお話していこうと思います!
人間というのはけなすのは楽、褒めるのは難しい
不思議なもので、私達は、他人のあらさすような言葉、けなす言葉、叱る言葉と言うのはさほど苦労もなく出てきます
でも「いいところを言おう」と言うとこれが、なかなかできるものではないのです
すらすら言えるなんてもってのほか!
人間は、他人を比較して成長しようとする習性があるようです
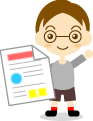 >
>
「もっと頑張ろう」「まだまだこのままじゃ駄目だ」と!それが、人類を背町させる原動力に違いありません
「褒めること」を意識しましょう
ある校長先生が小学校の6年生に質問をしたそうです!
「あなたのいいところは何ですか?」と。
すると、「分からない」とか答えられない子がほとんどだったそうです
逆に「悪いこと」はたくさん出てくるそうです
誰かに褒められた経験、認められる経験が不足している子が、多くいます!
少し勘違いしてほしくないことは、「褒めること」は子どもを甘やかす、叱らないということではなくて、「認めてあげること」と言うことです
どんどん、こどもの心にマルをつけてあげましょう。
それは、心のエネルギーを送るということです
次回は、今回の続きの「どんなふうに褒めていけばいいのか」を話していこうと思います!
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純

POWERS代表の狩俣です

今回も、こどもの成長がうかがえる感動のストーリーをお届けしたいと思います

ある記事に載っていたものなんですが、かなり素晴らしいものだと思ったので載せてみました


もうすぐ2才になるあずちゃん。このごろ家でのいたずらぶりがあまりにもひどい。ベランダから、おもちゃを次々に投げたり、部屋のすみっこでわざとおしっこをしたり…。いくら叱ってもまたやるので、ママはもう気が変になりそう。1ヶ月前に断乳に挑戦してから、こんな調子です。結局断乳はとりやめたのですが、やはりストレスになったのでは?とママは重い気持ちでした。
ところが、よくよくあずちゃんの思いをたぐっていくと、その本音は全く違うところにあることがわかったのです。ママの想像とはまったく逆で、断乳がうまくいかなかったこと、りっぱなお姉さんになりそこなったくやしさが、あずちゃんのいらだちの原因だったのです。その思いに気づいたママは、断乳に再挑戦。みごと乗り越えたあずちゃんは、すっかり落ちつき、グンとお姉さんらしい、自信に満ちた顔つきになりました。

こども達は自分でいろいろ成長して自分を高めていこうと必死です

自分で、いろいろ挑戦していこうとしていることがわかります

この記事を読んでいただいているあなたも、いろいろ挑戦していきましょう

感動の話はこのぐらいにして、今日のテーマは「こどもの心にたくさんのマルをつけよう!」です

話に入る前にまず、最初に質問に答えてこどもがの事をどれだけ分かっているかの確認のテストをしたいと思います!

幼稚園の先生や、保育園の先生や小学校の先生などを目指している学生さんや、現役で教員をしていらっしゃる方にも是非、このテストをお勧めします


「子どものいいとこリスト」

Q1.うちの子は____が得意です!
Q2.うちの子は____ができます!
Q3.うちの子はいつも____して偉い!
Q4.うちの子は____と人に褒められます!
Q5.うちの子は____をするのが上手です!
Q6.うちの子のいいところはズバリ____です!
Q7.私はうちの子を____と自慢できます!
Q8.私はうちの子の____が大好きです!
Q9.うちの子の____なところは夫に似て良かった!
Q10.うちの子の_____なところは私に似て良かった!
さて、この質問にさらっとこたえられたでしょうか?

さらっと答えられたら、あなたはこどもの事を良く見ていて、良く分かっている、つまりこどもの「いいところ探し」をしっかりしているということです

分かっているけど、書けない人は口に出す習慣がなかったのかもしれません

こどもにどんどん口に出してあげてほしいと思います!

1つ名言を残しておきましょう

「口に出さずは相手に気持ちは伝わらない!」 by suguru karimata

結構前に、こどものセルフイメージを高めることが大切と言うことでたくさんのマルをつけてあげようと話しました

今回も、こどもをほめることについてお話していこうと思います!

人間というのはけなすのは楽、褒めるのは難しい

不思議なもので、私達は、他人のあらさすような言葉、けなす言葉、叱る言葉と言うのはさほど苦労もなく出てきます

でも「いいところを言おう」と言うとこれが、なかなかできるものではないのです

すらすら言えるなんてもってのほか!
人間は、他人を比較して成長しようとする習性があるようです

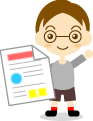 >
>「もっと頑張ろう」「まだまだこのままじゃ駄目だ」と!それが、人類を背町させる原動力に違いありません

「褒めること」を意識しましょう

ある校長先生が小学校の6年生に質問をしたそうです!
「あなたのいいところは何ですか?」と。
すると、「分からない」とか答えられない子がほとんどだったそうです

逆に「悪いこと」はたくさん出てくるそうです

誰かに褒められた経験、認められる経験が不足している子が、多くいます!
少し勘違いしてほしくないことは、「褒めること」は子どもを甘やかす、叱らないということではなくて、「認めてあげること」と言うことです

どんどん、こどもの心にマルをつけてあげましょう。
それは、心のエネルギーを送るということです

次回は、今回の続きの「どんなふうに褒めていけばいいのか」を話していこうと思います!

参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
2012年01月20日
こどものやる気アップ part20
みなさん!
こんにちは
代表の狩俣です!
最近、素晴らしい話を聞きました
私狩俣が住んでいる団地のお母さんから聞いたお話なんですが、とてもいい話だったので話をお話したいと思います!
そのお母さんは涼くんというお子さんがいます!
お母さんはお仕事に出ることになり、涼くんを保育園に預けることにしました 毎朝の嫌なことのたねは、涼くんが保育園に仮面ライダーの人形をもっていきたがること。「家のおもちゃは持ってこない」というのが、保育園の決まりなのですが、涼くんは、ガンとして受けつけません
毎朝の嫌なことのたねは、涼くんが保育園に仮面ライダーの人形をもっていきたがること。「家のおもちゃは持ってこない」というのが、保育園の決まりなのですが、涼くんは、ガンとして受けつけません 毎朝毎朝、「おいていく・いかない」の押し問答。あげくの果ては、人形をとり上げたママと、泣きわめいて
毎朝毎朝、「おいていく・いかない」の押し問答。あげくの果ては、人形をとり上げたママと、泣きわめいて のお別れです。「まだまだ赤ちゃんなんだなあ。もうちょっとしっかりしてくれないと・・・
のお別れです。「まだまだ赤ちゃんなんだなあ。もうちょっとしっかりしてくれないと・・・ 」と、ママは憂欝です。「仕事に出るのが早かったのかなあ」と、少し後悔していました
」と、ママは憂欝です。「仕事に出るのが早かったのかなあ」と、少し後悔していました
でも、しばらくしてわかったことは・・・ 。仮面ライダーのお人形は、実は、涼くんの「りっぱなお兄さんになるぞ
。仮面ライダーのお人形は、実は、涼くんの「りっぱなお兄さんになるぞ !」という気持ちの象徴だったのです
!」という気持ちの象徴だったのです ママとのバイバイがとっても寂しい。でも、そんな弱虫じゃいけない
ママとのバイバイがとっても寂しい。でも、そんな弱虫じゃいけない 不安でいっぱいの保育園にも、仮面ライダーのように強く、勇ましく、出動していくぞ
不安でいっぱいの保育園にも、仮面ライダーのように強く、勇ましく、出動していくぞ お人形は、そんな決意のあらわれだったのです。涼くんの本音に気づいたとき、ママは少しホロッとしてしまいました
お人形は、そんな決意のあらわれだったのです。涼くんの本音に気づいたとき、ママは少しホロッとしてしまいました そして、ママの気づきと同時に、不思議なことに、涼くんはお人形をおいていけるようになったのです
そして、ママの気づきと同時に、不思議なことに、涼くんはお人形をおいていけるようになったのです
なんか、子どものたくましい姿がわかりますよね
お母さん方は子育てとはお母さん自身が子どもを育てていかなきゃという感じを受けてませんか?
それは、間違いです
子どもは「お兄さんになりたい。お姉さんになりたいと」頑張っているんです!
自分で成長しようとする事、悔しがりますし、悲しみますし、いわば自己成長力が備わっているわけです
こどもの困った行動の裏には「成長したい」と言う気持ちがあるのです
それをサポートしてあげるのがお母さんや保護者の役割です!子どもはちゃんと考えているんです!

ちょっと前節が長くなりましたが、今回のお話に戻りましょうか
なんか、いい話で気持ちもすがすがしくなったところで・・・!
今回は前回の続きの「子ども自身が読む!心のエネルギーの補給の仕方」についておはなしします
今回も、お母さんとお子さん一緒に読んでいただけると嬉しいです(^-^)
大学生で教員や保育士、幼稚園教諭を目指している方も必見です!
こういった知識は絶対先生になった時に役に立つ事です
前回の記事をまだ、ご覧になっていない方は、ご覧になってからこの記事をご覧ください
「自分をほめる」
自分ってホント頑張っているさー!偉いさー!もしかしたらしーじゃーの中でも結構真面目にやっているはずよ!バスケこんなにうまくなったさーや!だある、俺は、やっけーチューバーだばーよ!っと自分で自分の努力を認めて褒めてあげよう
自分の頑張りはだれよりも自分が一番わかっているんだから
謙虚はいらない、思いっきりほめてあげよう
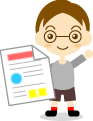
「友達をほめる」
「○○くん、○○ちゃん、この前のピアノの演奏会とても良かったと思うよ!あのサッカーのシュートかっこよかったよ!妹の面倒をちゃんと見て偉いと思った!」など、いいと思ったことはお友達に言ってあげよう
友達の心にもエネルギーを注入してあげれば、いつか自分にもエネルギーが帰ってくるに違いないよ

「自分だけの楽しみをもとう」
近所の犬とじゃれあう!河原の芝生に寝転がって空を見上げる!プラモデルを作る!音楽を聴く!などたくさんの自分だけの楽しみを持とう!
自分の好きな世界をもっと豊かにしよう
「誰かに相談する」
親や友達でも、学校の先生でもカウンセラーでも誰でもいいから勇気を持って「ちょっと話を聞いてほしいことがあるばーよ!きいてくれん?」「ちょっと話を聞いてほしいことがあるんだけど、聞いてくれないかしら?」と聞いてみて
きっと心が落ち着くと思うよ
「体を休める」
健康な体は、健康な心の基本。まずは、おもいっきし寝よう
疲れていると、なかなかやる気が出てこないもの、音楽を聴きながらゆっくり休もう
「部屋を片付けよう」
少し面倒くさいかもしれないけど、机の上や部屋を綺麗に掃除してみよう
部屋がスッキりすると、気持ちもスッキリするよ
壁のポスターやぬいぐるみの位置を換えてみるだけでも、気分転換になるよ

どうでしたか?
これを実践して、やる気をアップしていきましょう!
これで、明日からやる気満々で学校で遊べるし、勉強もはかどるに違いない
お母さんもお子さんに教えてあげてください!
次回は「こどもの大きな丸をつける」についてお話していきたいと思います!
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
こんにちは

代表の狩俣です!
最近、素晴らしい話を聞きました

私狩俣が住んでいる団地のお母さんから聞いたお話なんですが、とてもいい話だったので話をお話したいと思います!
そのお母さんは涼くんというお子さんがいます!
お母さんはお仕事に出ることになり、涼くんを保育園に預けることにしました
 毎朝の嫌なことのたねは、涼くんが保育園に仮面ライダーの人形をもっていきたがること。「家のおもちゃは持ってこない」というのが、保育園の決まりなのですが、涼くんは、ガンとして受けつけません
毎朝の嫌なことのたねは、涼くんが保育園に仮面ライダーの人形をもっていきたがること。「家のおもちゃは持ってこない」というのが、保育園の決まりなのですが、涼くんは、ガンとして受けつけません 毎朝毎朝、「おいていく・いかない」の押し問答。あげくの果ては、人形をとり上げたママと、泣きわめいて
毎朝毎朝、「おいていく・いかない」の押し問答。あげくの果ては、人形をとり上げたママと、泣きわめいて のお別れです。「まだまだ赤ちゃんなんだなあ。もうちょっとしっかりしてくれないと・・・
のお別れです。「まだまだ赤ちゃんなんだなあ。もうちょっとしっかりしてくれないと・・・ 」と、ママは憂欝です。「仕事に出るのが早かったのかなあ」と、少し後悔していました
」と、ママは憂欝です。「仕事に出るのが早かったのかなあ」と、少し後悔していました
でも、しばらくしてわかったことは・・・
 。仮面ライダーのお人形は、実は、涼くんの「りっぱなお兄さんになるぞ
。仮面ライダーのお人形は、実は、涼くんの「りっぱなお兄さんになるぞ !」という気持ちの象徴だったのです
!」という気持ちの象徴だったのです ママとのバイバイがとっても寂しい。でも、そんな弱虫じゃいけない
ママとのバイバイがとっても寂しい。でも、そんな弱虫じゃいけない 不安でいっぱいの保育園にも、仮面ライダーのように強く、勇ましく、出動していくぞ
不安でいっぱいの保育園にも、仮面ライダーのように強く、勇ましく、出動していくぞ お人形は、そんな決意のあらわれだったのです。涼くんの本音に気づいたとき、ママは少しホロッとしてしまいました
お人形は、そんな決意のあらわれだったのです。涼くんの本音に気づいたとき、ママは少しホロッとしてしまいました そして、ママの気づきと同時に、不思議なことに、涼くんはお人形をおいていけるようになったのです
そして、ママの気づきと同時に、不思議なことに、涼くんはお人形をおいていけるようになったのです
なんか、子どものたくましい姿がわかりますよね

お母さん方は子育てとはお母さん自身が子どもを育てていかなきゃという感じを受けてませんか?
それは、間違いです

子どもは「お兄さんになりたい。お姉さんになりたいと」頑張っているんです!
自分で成長しようとする事、悔しがりますし、悲しみますし、いわば自己成長力が備わっているわけです

こどもの困った行動の裏には「成長したい」と言う気持ちがあるのです

それをサポートしてあげるのがお母さんや保護者の役割です!子どもはちゃんと考えているんです!

ちょっと前節が長くなりましたが、今回のお話に戻りましょうか

なんか、いい話で気持ちもすがすがしくなったところで・・・!
今回は前回の続きの「子ども自身が読む!心のエネルギーの補給の仕方」についておはなしします

今回も、お母さんとお子さん一緒に読んでいただけると嬉しいです(^-^)
大学生で教員や保育士、幼稚園教諭を目指している方も必見です!
こういった知識は絶対先生になった時に役に立つ事です

前回の記事をまだ、ご覧になっていない方は、ご覧になってからこの記事をご覧ください

「自分をほめる」
自分ってホント頑張っているさー!偉いさー!もしかしたらしーじゃーの中でも結構真面目にやっているはずよ!バスケこんなにうまくなったさーや!だある、俺は、やっけーチューバーだばーよ!っと自分で自分の努力を認めて褒めてあげよう

自分の頑張りはだれよりも自分が一番わかっているんだから

謙虚はいらない、思いっきりほめてあげよう

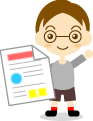
「友達をほめる」
「○○くん、○○ちゃん、この前のピアノの演奏会とても良かったと思うよ!あのサッカーのシュートかっこよかったよ!妹の面倒をちゃんと見て偉いと思った!」など、いいと思ったことはお友達に言ってあげよう

友達の心にもエネルギーを注入してあげれば、いつか自分にもエネルギーが帰ってくるに違いないよ


「自分だけの楽しみをもとう」
近所の犬とじゃれあう!河原の芝生に寝転がって空を見上げる!プラモデルを作る!音楽を聴く!などたくさんの自分だけの楽しみを持とう!

自分の好きな世界をもっと豊かにしよう

「誰かに相談する」
親や友達でも、学校の先生でもカウンセラーでも誰でもいいから勇気を持って「ちょっと話を聞いてほしいことがあるばーよ!きいてくれん?」「ちょっと話を聞いてほしいことがあるんだけど、聞いてくれないかしら?」と聞いてみて

きっと心が落ち着くと思うよ

「体を休める」
健康な体は、健康な心の基本。まずは、おもいっきし寝よう

疲れていると、なかなかやる気が出てこないもの、音楽を聴きながらゆっくり休もう

「部屋を片付けよう」
少し面倒くさいかもしれないけど、机の上や部屋を綺麗に掃除してみよう

部屋がスッキりすると、気持ちもスッキリするよ

壁のポスターやぬいぐるみの位置を換えてみるだけでも、気分転換になるよ


どうでしたか?
これを実践して、やる気をアップしていきましょう!

これで、明日からやる気満々で学校で遊べるし、勉強もはかどるに違いない

お母さんもお子さんに教えてあげてください!
次回は「こどもの大きな丸をつける」についてお話していきたいと思います!

参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純
2012年01月18日
こどものやる気アップ part19
みなさん
こんにちは
POWERS代表狩俣です
今回は子どもが自分で読んでみる記事として「心のエネルギー」の補給についてお話していきたいと思います

もし、君が「最近、全然やる気が出ないと」思っているなら、きっと心のエネルギーが足りていない証拠だよ

心のエネルギーは、車に例えるとガソリンのようなもので、「頑張ってみよう」と思う時になくてはならないものだよ
どんなに運転が上手くても、ガソリンがなければ力は発揮されないよ
心のエネルギーをためないと心や体が病気になってしまうこともあるんだよ
でも、大丈夫
心のエネルギーには補給する事が出来るから
次のやれそうなことから実行してみよう

①家族に甘えてみる
「僕は、もう小さくないからそんなことできるか 」と思っている君
」と思っている君
誰だって心がピンチなときはあるんだよ!
そんな時に家族に甘えることは大事なことで、基本だと思う
君の甘えを受け止めてくれる家族があってほしいよ
②仲間を作る
一人でもいいし、多ければなおいい!
友達が居ないなら、先生や近い席の人に友達になってもらおう
ただし、本当の友達ができるまでの間だよ
できたら楽しいことを共有しよう!

③友達とおしゃべりする
テレビでも、スポーツでも、なんでも友達と話題をつくってたくさんおしゃべりしよう
④友達と思いっきり遊ぶ
時には大声を出して笑ったりすれば、体の内側から元気が湧いてくると思うよ
おにごっことかかくれんぼとか!

⑤褒めてもらう
自分のやった事、できたことなどどんなに小さなことでも、お母さん、お父さん、先生にほめてもらおう
「僕、テスト100点とったばーよ、みてみ、これ!」とかそんな感じで

今回はこのへんで、また次回に持ち越しということで
是非、上の心のエネルギーがたまる方法を実践してみてくださいね
参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純

こんにちは

POWERS代表狩俣です

今回は子どもが自分で読んでみる記事として「心のエネルギー」の補給についてお話していきたいと思います


もし、君が「最近、全然やる気が出ないと」思っているなら、きっと心のエネルギーが足りていない証拠だよ


心のエネルギーは、車に例えるとガソリンのようなもので、「頑張ってみよう」と思う時になくてはならないものだよ

どんなに運転が上手くても、ガソリンがなければ力は発揮されないよ

心のエネルギーをためないと心や体が病気になってしまうこともあるんだよ

でも、大丈夫

心のエネルギーには補給する事が出来るから

次のやれそうなことから実行してみよう


①家族に甘えてみる
「僕は、もう小さくないからそんなことできるか
 」と思っている君
」と思っている君
誰だって心がピンチなときはあるんだよ!
そんな時に家族に甘えることは大事なことで、基本だと思う

君の甘えを受け止めてくれる家族があってほしいよ

②仲間を作る
一人でもいいし、多ければなおいい!
友達が居ないなら、先生や近い席の人に友達になってもらおう

ただし、本当の友達ができるまでの間だよ

できたら楽しいことを共有しよう!

③友達とおしゃべりする
テレビでも、スポーツでも、なんでも友達と話題をつくってたくさんおしゃべりしよう

④友達と思いっきり遊ぶ
時には大声を出して笑ったりすれば、体の内側から元気が湧いてくると思うよ

おにごっことかかくれんぼとか!

⑤褒めてもらう
自分のやった事、できたことなどどんなに小さなことでも、お母さん、お父さん、先生にほめてもらおう

「僕、テスト100点とったばーよ、みてみ、これ!」とかそんな感じで


今回はこのへんで、また次回に持ち越しということで

是非、上の心のエネルギーがたまる方法を実践してみてくださいね

参考文献:「わが子のやる気スイッチはいつ入る?」 著者:菅野 純